


センムの"真の部分"を信じて醸し続けてきた杜氏・太田茂典さん➀
全量純米という本質的な酒造りを追求しつつ、日本酒の持つ多彩な可能性を拓いてきた神亀酒造。独自の蔵の在り方は、先代蔵元の小川原良征さん(=センム)の強い信念によって築かれてきたものだ。その強靭な精神力を持つ蔵元を相手に、イエスマンになることなく、時には互角に意見を闘わせながらも、神亀ならでは酒造りを実践してきたのが現杜氏の太田茂典さんだ。センムと出会い、共に過ごした歳月は18年間。「強烈な存在感だった」と振り返る蔵元との日々をお聞きした。
熱心な仕事ぶりを見込まれ、初年度にいきなりの杜氏代理に
蔵元のカリスマ性ゆえか、神亀という酒は“センムの酒”としてイメージされることが多かった酒である。むろん、酒造りの信条、味わいの基礎はセンムによって造られたものだが、そのセンムの思い描いた理想の酒に向って、託された米を酒へと醸し続けてきたのが、杜氏の太田茂典さんだ。
太田さんは、埼玉県生まれ。大学を卒業後に就いた職業は、広告代理店のコピーライターだった。広告の共同制作は楽しい仕事だったが、酒造りの仕事に惹かれ、蔵人へと転身したのは30歳のとき。奈良の3000石規模の酒蔵で5年間働いた後に神亀酒造へ。全量純米蔵という在り方を実現させたセンムに共鳴しての蔵入りからは、すでに4半世紀が経過した。
太田さんが神亀酒造に入社した1999年の醸造年度は、前任の越後杜氏・原昭二さん(故人)が体の不調から急きょ酒造りから抜けることになった年で、蔵内は何かと落ち着かない状態だった。原杜氏の休職と前後して麹担当の蔵人も退職、酒造りが始まってから人手不足に陥った蔵の中には、当時50代のセンムも戦力として加わっていた。そのセンムからの突然の任命で蔵入り初年度の太田さんは、杜氏代理をつとめることになる。現場での太田さんの仕事ぶりが見込まれてのことであろうが、にしても、いきなりの大役。
入って早々に配置された酛屋の仕事、そこに退職者の穴を埋める形での麹屋の仕事が加わり、さらには杜氏代理という重圧。神亀酒造の麹造りは全量が麹蓋、つまりは一番容量の小さな道具で、手のかかる作業を繰り返すことになる。「麹蓋の作業で麹造りが好きになった」と語る太田さんではあるが、初年度は心身共にハードな数ヶ月間を過ごすことになった。


翌2000年の醸造年度からは、現場に復帰した原杜氏のもとで3造りを経験。原杜氏が引退した2003年からは、再び太田さんが蔵を統率し、酒造技能検定1級の試験に合格した2005年度からは、正式に杜氏職を任命された。
「その前に南部杜氏の資格選考試験を1度落ちてるんですよね。そしたら、センムが『落ちたのか。1級に受かったら杜氏にするから頑張れよ』って言ってくれて。それで翌年に両方受かって正式に杜氏になりました」。
蔵に入った頃、太田さんが意外だと感じたのは、鑑評会の類は否定しているだろうと思っていたセンムが「勉強になるから」と、埼玉県の鑑評会の会場に連れて行ってくれたことだ。
「出品酒は全部アルコール添加の吟醸酒なんですけど、センムは『こういう酒も技術の極致なんだから、ちゃんと勉強しておけよ』と。あれ、センムも頭からアル添の酒を否定しているわけではないんだなと思いました。あと、『審査の先生たちがうちの酒を飲みたいだろうから、持って行って飲ませてやれ』とも。うちの酒は入賞もしていないのに、すごい上から目線で言ってましたね(笑)」。

太田さんがセンムと過ごした歳月は、1999年秋から2017年春までの18年間だ。親切で面倒見の良いセンム、情の深いセンム、真摯に酒造りに向き合うセンム、己の信念を貫きとおすセンム、納得のいかないことには激高してしまうセンム。さまざまなセンムを太田さんは見つめてきた。蔵元と杜氏としての二人の関係は、おおもとのところでの深い共感と信頼は持ち合いながら、しかし、つねに平穏無事というものではなかった。
「センムは、怒ると走って追いかけてくるような激しい人だったですからね」。
それは、比喩ではない。ある年の冬、太田さんがインフルエンザの予防接種を拒否した時には、センムは「なんでだ」と怒り、太田さんのあとを追いかけてきたという。
「ほんとに走って、追いかけてきましたからね(笑)」。
それが予防接種の話ならまだしも、酒造りについて意見の相違が生じてしまうと、互いに口をきかなくなるような状態になることもあった。「そういう時は、美和子さんに間に入ってもらったりもしましたね。お互いに美和子さんに伝言して(笑)」。


センムは、醸造家としての確固たる信条を持っていた人だ。そのひとつに「神亀酒造は、速醸酛のみで酒造りをおこなう」という決定事項があった。センムには、先人が苦労して築きあげてきた近代の醸造法へのリスペクトがあったからだ。しかし、そのセンムに対して太田さんが伝えた「速醸酛だけではなく、山廃酛仕込みの酒を造りたい」という提案は、受諾までには10年もの歳月を要した。
酒造りを続けていく上で太田さんには「速醸酛と山廃酛とでは乳酸の成り立ちが違う。その違いを学ばなければ、造り手として前に進めない」という気持ちがあったという。けれどもセンムにも「速醸であっても打瀬(※)を長くとれば、良い酸は得られる」という確信がある。山廃酛の導入については膠着状態が続いたが、最終的には2012年、東日本大震災の翌年に「東北で被災して、酒を造りたくても造れない状況の蔵もある中で、酒を造ることができる自分たちは、やりたい酒造りを試していきたい。なんとか、やらせてください」と、太田さん曰く「ごり押し」で説得。それをセンムが受け入れ、山廃酛による仕込みも始まることになった。
※打瀬(うたせ)
酒造りのスターターとなる酒母の温度操作。仕込み後に温度を下げ、低温(6℃以下)の厳しい状況下でも生き残る生命力の強い酵母を育成する目的がある。

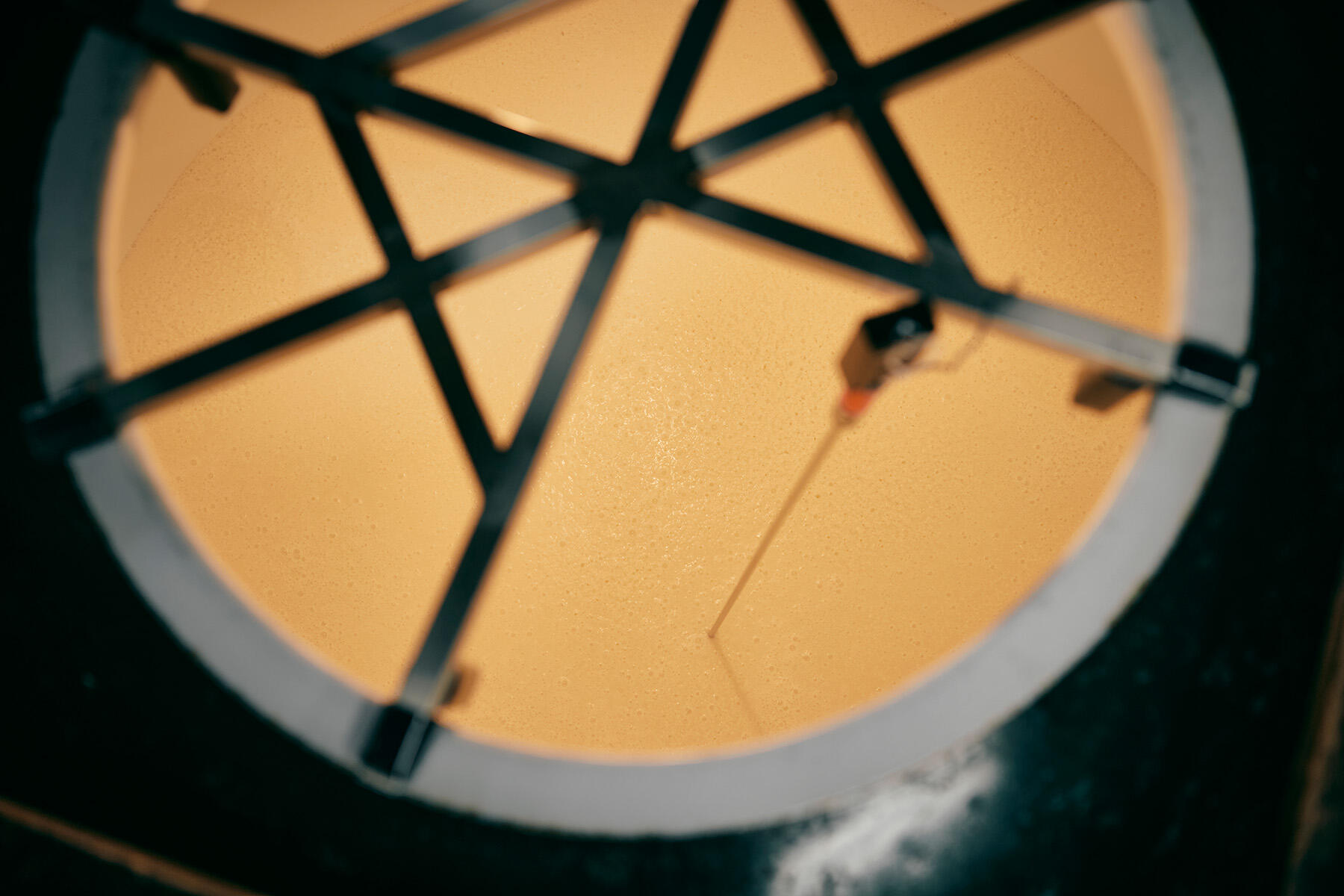
もうひとつ、意見が分かれたのは、熟成酒の出荷についてだ。熟成酒に力を入れるセンムは、少しでも長く酒をタンクに留めておきたい。だが、その量が多すぎて、新しい酒を仕込むためのタンクが足りなくなっている。そのことを太田さんは、センムに訴えるのだが、タンクの中の酒は出荷されずに眠るばかり。「タンクの配置図をセンムの机の上に置いたりして。それでタンクが足りないと伝えようとしたんですが、でも、そうすると、センムはタンクを空けるのではなくて、新しくタンクを買っちゃうんですよね(笑)」。
かように蔵の中での意見の相違は時折生じていたものの、しかし、太田さんが持ち続けていたセンムの基本姿勢に対する信頼は揺らぐことはなかったという。
「センムの真の部分、まっすぐなセンムを知っていますから。自分だけじゃなくて、ほかの蔵人たちだって、センムに共感して入ってきている人ばかりですから。そこはブレなかったと思うんですよね」。
センム自身も太田杜氏と蔵人の造る酒を信頼し、愛飲していた。
「いろいろと喧嘩をしましたけど、造ったお酒に関して文句を言われたことは、一度もなかったですね。センムが『おおっ、太田!』って大声出してるから、怒られるのかなと思ったら『すごい、いい酒できたな』と。それは嬉しかったですね。造っている者として」。

文:藤田千恵子 撮影:伊藤菜々子









