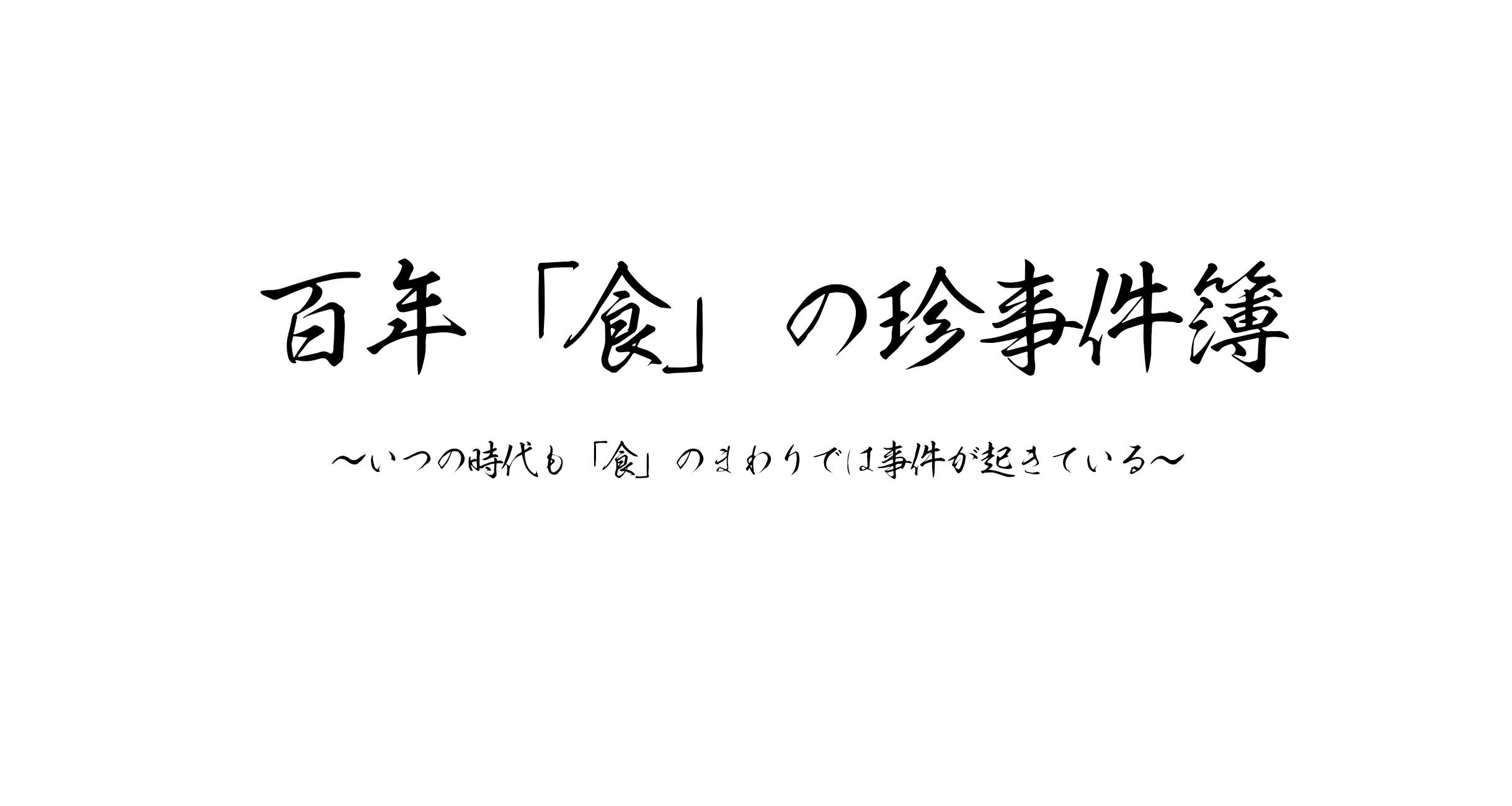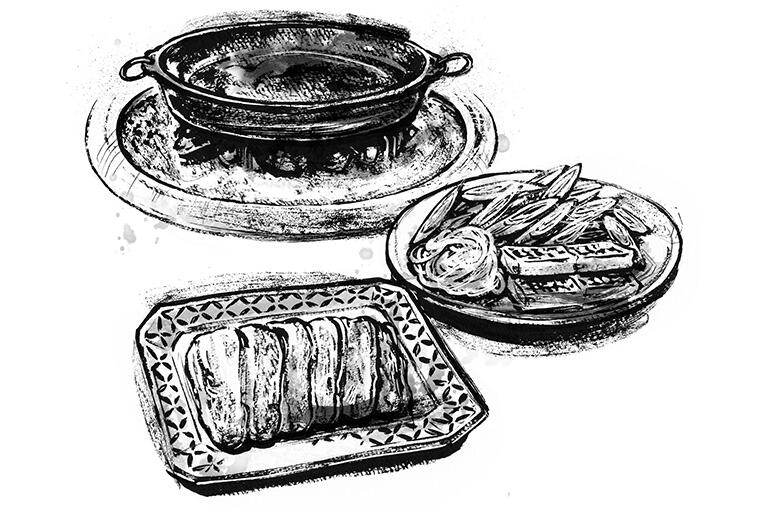熊笹でフランス人流血事件
時は明治初頭の激動の時代。各国の食習慣の共通認識もない中で起きた事件から得られる教訓とは?本当にあった「食」にまつわる珍事件を、フードアクティビストの松浦達也さんが掘り起こす読み物連載。なぜその珍事件が起きたのか?時代背景の考察とともにお届けします。
文明開化ごろのお話
郷に入りては郷に従え、という格言は食の世界のためにある言葉だと言ってもいいかもしれない。各国各地にそれぞれの作法があり、慣れないアウェイの地では身を預けるつもりで目をつぶってえいやっ!と五体投地をして注意を払い、つぶさに観察をし、現地の流儀に合わせる。いつの時代もアウェイと清水の舞台は恐ろしいものだ。
さて、異文化が流入してきた明治の文明開化の頃と言えば、文化的にはそこいら中アウェイだらけ。日本人はそれまでにない食事のスタイルに戸惑い、日本にやってきた欧米人もまた奇異にも映る東洋の島国の習慣に目を白黒させていた。「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」ということわざにもあるように、新しいものに触れたとき「いっときの恥」と割り切ったふるまいが難しいのは、知ったかぶりをテーマにした落語の「転失気」という演目からもよくわかる。
さて本題。明治後期の秋口、新聞にこんな記事が載った。
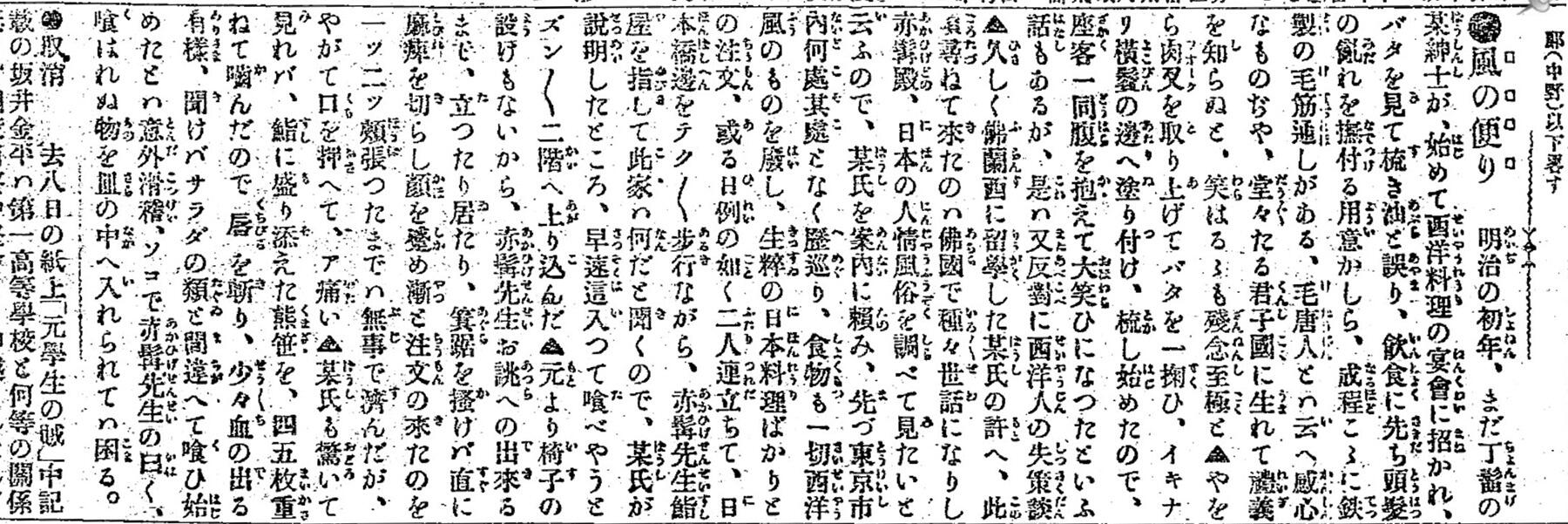
- 風の便り
- 明治初頭、西洋料理の会食に招かれたちょんまげ姿の紳士が、バターを鬢付け油、フォークを櫛だと勘違いしてみだしなみを調え始めたという笑い話があるが、逆の例もある。フランス留学歴のある日本人男性のもとにフランス人が遊びにやってきた。
聞けば、日本の人情風俗(人の心持ちと社会のならわし)を調べたいとのことで、生粋の日本料理ばかりを食べ歩いていたところ、鮨店が気になったらしく二階へとずんずん上がり込む。ところが椅子がないのであぐらをかいても足がすぐしびれ、立ったり座ったり。
挙げ句、待ちに待った鮨が来たので頬張ったところ、唇を切って流血騒動に。どうやら一緒に盛ってあった熊笹をサラダと間違えて4~5枚重ねて口に入れたよう。「食べられないものが皿の上にあっては困る」と言い残したという。
異文化流入時代の教訓
文化の壁は、コミュニケーションで乗り越えられる――。多様であることが当たり前のいまならまだしも、ことは100年以上前の噺。恥ずかしさが先に立って、ついもののわかったふりをしてしまうような場面だってあったろう。
記事冒頭の「某紳士」の振る舞いなどは実に象徴的。「ざんぎり頭を叩いてみれば、文明開化の音がする」と言われるほど新しい文化が加速度的に流入するなか「まだちょんまげ」と揶揄されてしまう昔気質の男性にとって「作法がわからなければ尋ねる」という、腰の低い振る舞いは高いハードルだったに違いない。
それにしても、テーブルに置いてあるバターを鬢付け油、フォークを櫛と間違えて横髪あたりをととのえた……つもりが周囲から失笑を買ってしまう。現代なら顔から火が出てしまいそうな知ったかぶりだが、当時の世相からはそうとばかり言えないところもある。
現代よりも遥かに情報インフラが脆弱だった当時は、情報が持つ価値は高く、新しい文化や異文化の作法を身につけるのは難しい。情報格差が大きな時代に、知識を持たざる者を指して笑いを取るのは、ある種の階級社会を象徴するかのようでもあり、情報を持たざる者を珍奇な笑いの対象としてしまう。その後も昭和の頃まで、いやもしかするといまもどこかで続く、下層に目を向けさせる未成熟なメディアの常套手段と言えるのかもしれない。
同じように当時来日したフランス人が鮨の食べ方を知らなかったとしても無理からぬことだ。にも関わらず、新聞には「東京市内どこそことなく巡り」「一切西洋風のものを廃し、生粋の日本料理ばかりとの注文」「鮨屋を指してこの家は何だと聞くので、説明したところ、早速入って食べようとズンズン二階へ上がりこんだ」など少々険のある表現が並ぶ。
記事の端々ににじむフランス人男性への違和感は、文中での「赤髭(ひげ)」という表現よりも、さらに強い「黒船」に対するような畏怖を伴っていたとも考えられる。
記事のクライマックスは、あぐらで足がしびれてしまったフランス紳士が、鮨に添えられた熊笹も一緒にほおばって唇を切ってしまうシーン。
明治の頃の鮨店と言えばまだ屋台店も多く、小上がりで鮨が食べられる「内店」も出前中心の商売だった。当時の狭い家屋に、体躯の大きな西欧人が体を縮めるように慣れないあぐらで座らされ、しびれを切らせた挙げ句、未知なる葉っぱで口を切り文句を言うのも仕方なかろう。
冒頭の「郷に入りては郷に従え」には似た意味のことわざがいくつかある。よりストレートに戒めるなら「国に入っては、まず禁を問え」だろうか。見知らぬ文化に触れるときには、流血を伴うケガなどしないよう、慎重に振る舞いたい。訪れたその場には、かけがえのない大切な体験が待っているのだから。
文:松浦達也 イラスト:イナコ