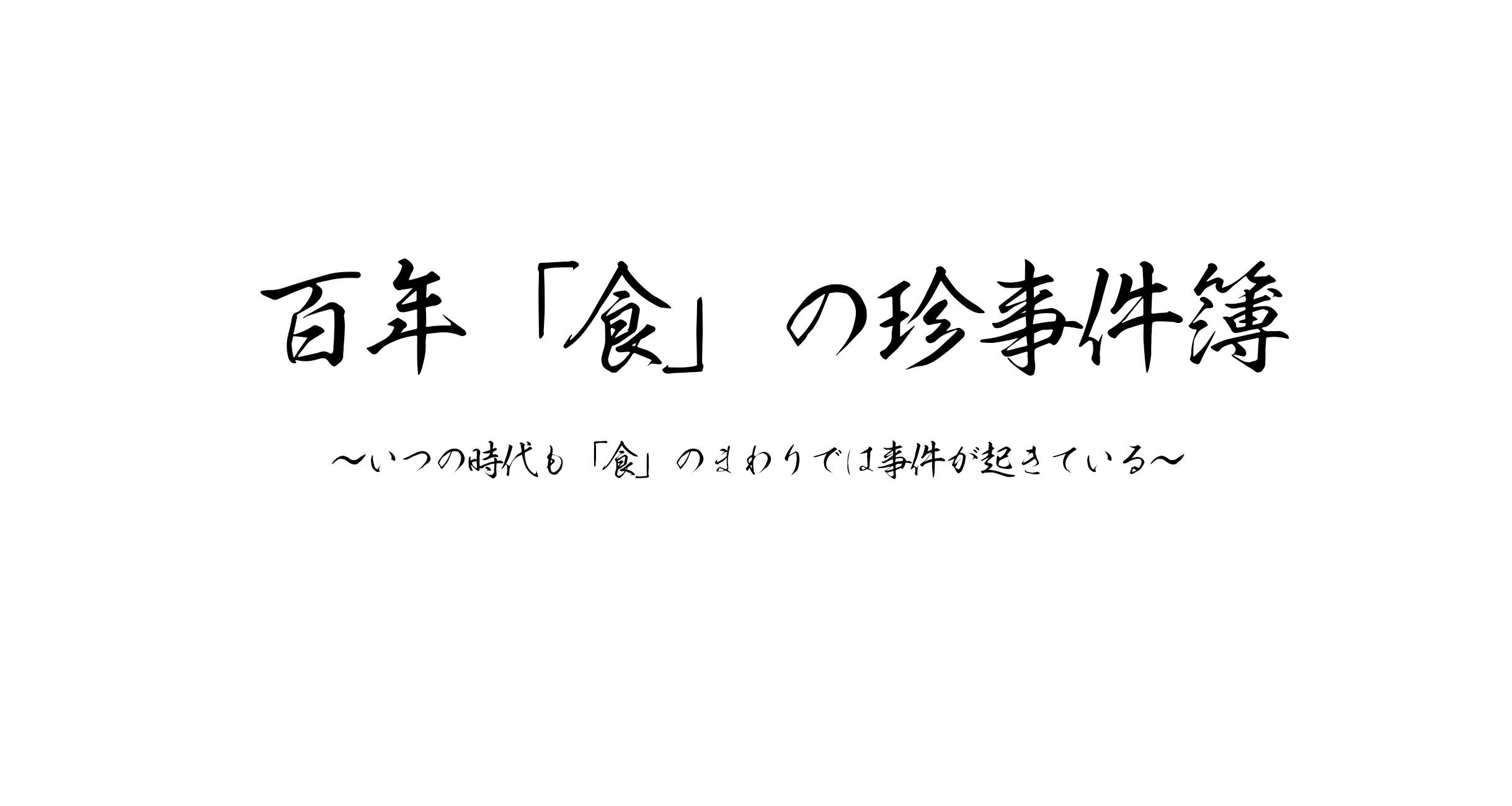重大な政治的判断が下された!?西園寺公望の「牛鍋会」
総理大臣を2度務めた西園寺公望が住まう首相官邸で開かれた「牛鍋会」。参加した面々を振り返ると、国を動かす中枢人物が密談していたのかと思いきや……。本当にあった「食」にまつわる珍事件を、フードアクティビストの松浦達也さんが掘り起こす読み物連載。なぜその珍事件が起きたのか!?時代背景の考察とともにお届けします。
猫も杓子も「牛鍋」時代
明治4(1871)年以降、都内には牛鍋店が次々開店し、明治10(1877)年には人口100万人の東京に550軒もの牛鍋店が軒を連ねた。人口1万人あたり、5.5軒。これは現代のコンビニチェーンと同じくらいの身近さだ。わずか数年で流行は爆発し、牛鍋ブームは文化として定着していった。
そんな世相を意識するのは政治家とて同じ。明治5(1872)年には、牛肉食の啓蒙のため、明治天皇自らが牛肉を試食している。国家元首が後押しする国の施策で、大衆の間でも爆発的な人気のコンテンツとなれば、傾倒する政治家が出てくるのは自然なことだが、次のニュースにはちょっと違和感がある。
[日曜付録]揮毫 「牛鍋の会」 西園寺首相官邸で開催

- ことのあらまし
- 2月9日永田町の首相官邸で「牛鍋の会」というものが開かれた。西園寺公望首相がかつて公使としてベルリンに住んでいたときに、公使館員や在留邦人の要人を集めて牛鍋と日本酒を取り寄せ、無礼講で開いた宴会を日本で開催した記念の会だった。
当日集まったのは西園寺首相ほか、旧・岩国藩藩主吉川家の末裔で外務官僚・貴族院議員の吉川重吉、山縣有朋の元秘書で政府系新聞の主筆・二宮熊次郎、官僚として次官クラスまで勤め上げて貴族院議員に勅撰された藤田四郎、外務官僚や大臣秘書官などを勤めた後に衆議院議員になる早川鉄冶、大本営の参謀であり、後に陸軍大将となる福島安正、衆議院議員で日本医学校初代校長の山根正次など、時の国家・政権を左右する錚々たる面々。
合作でしたためた揮毫には、上に大きく西園寺が「牛鍋之会」と書き表し、吉川はローマ字で「CK」、「回頭十五年間事」と書き、孤松生と署したのが二宮。以下「頑鉄云時是金」(藤田)、「天下横行」と書いて百練と署した早川、他「竹中さんもあり」(石渡)、「鴨緑暮雪」(安正)、その上の僧の絵は山根の筆だった。
牛鍋会は国運を左右する密談の場!?
複数の外務官僚に貴族院議員、さらには政府系新聞の主筆、陸軍大将に医学校の校長――。現代で例えるなら、官僚出身の複数のエリート議員3名と、新聞社の社長、軍部……はないので防衛省の副長官、医大の総長兼議員というようなメンバーだろうか。
平日の金曜日(明治から昭和の頃、休日は日曜・祝日のみで土曜の午前中は仕事が当然だった)から、これだけの顔ぶれを官邸に集めて、「無礼講」で牛鍋をつつく宴会を行い、あまつさえ新聞紙面の数段分を使って晴れ晴れと揮毫を開陳する。
現代の総理大臣がこんなことをしたら、メディアに追われてもおかしくない話なのに、読売新聞は喜々として特別なレイアウトを組み、揮毫を大扱いで報道している。
なんとも珍奇な話だが、その後も続いた牛鍋会は、なぜか報道されることが少なくなっていく。対して翌年に開催された泉鏡花や幸田露伴、森鴎外など錚々たる文士を招いての「雨声会」は、その後も繰り返し報道されるのに……。
魯山人も舌を巻いた西園寺公の美食ぶり
密談か親睦か、この「牛鍋会」とはいったいなんだったのだろうか。この年は日露戦争戦争の翌年。まだ時代はきな臭く、考え方によってはどこまでも謎は深まる。
しかし世情からではなく、西園寺公望という人をフィルターとしてこの件を見ると、拍子抜けするような仮説が成立してしまう。
西園寺は京都生まれで、幼少時から京料理に親しんだ。20代の頃フランスへ渡り、現地で10年を過ごした。当時の国会議員の歳費以上の公費に加えて、日本公使館で書記のアルバイトをしていたが、その給料は「右から左へと、カフェーや料理屋に流れ去るやう」だったという。
朝食から魚料理と2種の肉料理のコース、16時には魚料理、鳥料理、肉料理3種、野菜に菓子3種、果物3種コースを平らげ、その上夜食のローストビーフにも舌鼓を打ったりもした。
ドイツ公使着任後もドイツ料理が舌に合わず、暇さえあればパリに行っては美食三昧。帰国後もカトリックの聖地、「ルルドの聖水」をフランスから取り寄せ、ウイスキーの水割りに使った。井戸水から上水道へと移行する時期で、もちろん水を買う習慣などない時代のことである。
西園寺が常軌を逸した稀代の食いしん坊――美食に対する執着がおかしなほど強かったと考えると、平日に「牛鍋会」が行われたことも含めて、合点が行くのだ。実際、西園寺は「牛鍋会」や「雨声会」以外にも美食を伴う会合をたびたび催し"風流宰相"とも呼ばれた。
昭和の食通の巨人・北大路魯山人が昭和7(1932)年に「西園寺公の食道楽」という文を書き残している。
魯山人曰く「西園寺公は、かねて噂に聞いているように、たべものにはなかなかやかましい人」で「薪でたいた飯でなければ口にせぬ」と西園寺公の舌を評していた。
実際、西園寺のお抱え料理人は毎年のように入れ替わった。その中にはあの「京味」の店主、故・西健一郎氏の父である西音松もいたというし、天皇の料理番としても知られる秋山徳蔵も「何と恐ろしい舌」、「食べ物については、世にもやかましい人」と、西園寺の味覚におそれをなしたという逸話も残っている。
西園寺にとって牛肉は特別だった。ベルリン滞在時の同窓の会を「牛鍋会」と名付けただけでなく、明治天皇が牛肉を口にした明治5(1872)年より早く、明治以前の慶応3(1867)年東京・白銀に日本初のと畜場開設以前から、牛肉に親しんでいた。後に当時を回想して「そのうまかったことは、忘れられぬ」と綴ってもいる。
明治から大正にかけて激動の時代に国家を牽引し、庶民からも愛された"風流宰相"の西園寺公望。「最後の元老」とも呼ばれた男もまた、食にとりつかれし一人の食いしん坊だったのだ。
文:松浦達也 イラスト:イナコ