


ジビエ料理をはじめたい人へ。
-
- 連載 : あなぐまを食べる会
2018年12月4日に開催された「あなぐまを食べる会 リターンズ in 福井」。実はその晩餐会の前に、地元の料理人やサービスマン向けのジビエセミナーが催されていた。講師は東京・門前仲町「パッソ・ア・パッソ」の有馬邦明シェフ。福井の森が秘める食材の可能性を解説する。
「パッソ・ア・パッソ」有馬邦明シェフがジビエを解く
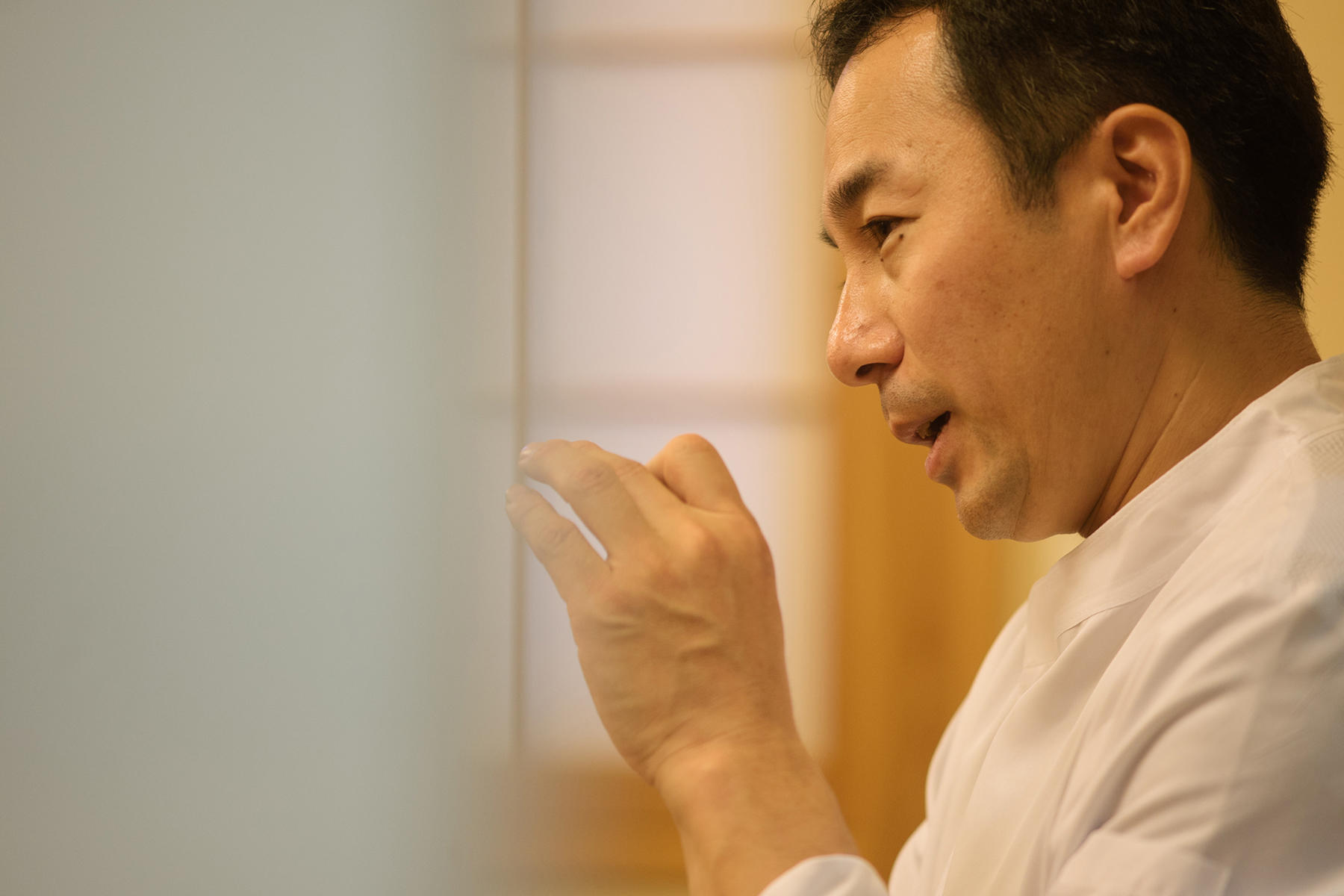
福井県福井市の山間に立つ「一乗谷レストラント」。2018年12月4日、一夜限りのジビエ・ディナー「あなぐまを食べる会 リターンズ in 福井」が始まる数時間前からレストランは密かな興奮に満ちていた。ジビエを熟知する料理人・有馬邦明シェフのジビエセミナーが行われていたのだ。有馬シェフはイタリアでの修業時代からジビエに触れており、日本におけるジビエ料理のトップシェフの一人である。

集まったのは、これからジビエ料理を始めたいけれど、疑問や不安もたくさん抱えているレストランや和食店のオーナーや料理人。すでにジビエ料理を提供しているレストランで働き、より理解を深めようとやって来たソムリエール。食にまつわる人々ばかりだ。
有馬シェフは、まず参加者に手製のパテやテリーヌの試食を促した。食材として使われているのは、地元で獲れたあなぐまや鹿をはじめ、猪やツキノワグマも。臭みとは無縁の味わいと、モツや脂まで余すことなく使う姿勢に、参加者はいきなり有馬シェフの料理哲学に引き込まれる。
初めて食べる味わいに、一同興味津々。全国的な傾向と同様に、福井でも鹿や猪は害獣駆除として捕獲頭数が増えており、食材としてよいイメージを持っていない人も多いという。だが「あなぐまの脂のケーキ!?」「臭くない」「食べやすい」「おいしい!」と、驚いたり感心したり。
そこで有馬シェフは言う。
「ジビエとは天然の環境がつくり出した宝です。木の実にきのこ、きれいな沢の水。これだけおいしいものが揃う山で育った動物たちがおいしくないわけないと僕は思うんです。ただ、筋肉の部位が大きいところはさっと火を通すだけでもおいしくいただけますが、バラや筋、内臓などはそうはいかない。それをいかに使って、おいしい料理にするかが僕たちの仕事です」
使ってみたくても「初めてのジビエ」には不安がつきもの
「今日来ていただいた方は、きっとジビエに対して期待よりも不安の方が大きいのではないでしょうか」
有馬シェフが投げかける。使いやすさ、食べやすさを考えられた食肉とはまるで違う天然の肉。初めて料理するには、その不安の解消が必要だ。毛はどうやってむしるのか。捌き方は。火入れはどんな加減か。そして、いいジビエにはどうしたら巡り会えるのか。
有馬シェフは、参加者から投げかけられた質問に次々答えていく。
「冬の雪に閉ざされたフランスで食べられ始めた頃とは時代は変わり、現代のジビエにおいては、僕は“硬い”“臭い”はあってはならないと考えています。それを避けるには、どんな餌を食べてどんな水を飲んでいるのか、雄か雌か、何歳なのかといったことから情報を得なければいけません。そして鹿なら首より上を狙って撃っているか。猟師さんは心臓が動いているうちに放血しているか。菌のいる部分をなるべく触わらずに内臓を処理しているか。そういったことがすべて味の違いに出てきます。食材にハートがある猟師さんと出会えるかがとても重要になってくるんです」
次々に参加者から質問が飛ぶ。
――今日はあなぐまの脂を使ったスイーツを試食しましたが、ほかのジビエの脂も使えるんですか?
「鹿の脂は冷めると蝋のように固まってしまい、人間より体温が高いために人間の体温では固形化してしまいます。対して、熊の脂は融点が低く料理に使うのに優れていますし、万能薬のようにも扱われています。猪、鴨も食用に優れています」
――殺菌のためにも火入れが必要だと思いますが、どんな温度帯がいいのでしょうか?
「ブルース・リーがいいことを言っています。“考えるな。感じろ”って。火入れもまさにそんな感覚です。本来は75度以上に上げなくてはいけません。そこで旨さ、柔らかさ、歯切れ、ジューシー感をクリアしていくのは難しいのですが感覚や経験がものをいうでしょう。鴨の胸肉だったら60~65度が適温だし、鹿肉は70度を超えるとピンク色から赤黒く変わって、パサパサのレバーのようになってしまいます」
――ワイン選びはどのようにしたらよいでしょうか?
「料理とワインはセットで郷土料理といえます。その土地でつくられたもの同士を組み合わせるのが前提だけど、僕の場合、下処理はほとんど日本酒を使っています。シェフに提供したいワインを味見してもらうのも手です。ソースにそのワインを使ったりして、料理の方をそのワインに寄せた味に仕上げてくれるでしょう」。

約1時間30分のセミナーは、あっと言う間に終了した。参加者の感想を聞いてみた。
「ピッコロ ターヴォロ」シェフ・籔内滉平さんは言う。「福井ではまだジビエを扱っている店が少ないので、地元産を扱えるなら他店との差別化ができると思います。そのためには勉強が必要です」。
「アルモニ ヴァンヴィーノ」調理長・加藤諭さんは、「すでにジビエは扱っていますが、まだ福井では猟師さんも食材というよりは害獣扱いしている方が多い印象。どんな環境で育ったのかという説明を料理と共に提供していきたいですね」。
「オステリア ダ シルヴァーノ」ソムリエール・小西光貴さんはこう願う。「ジビエはワインを楽しむのにぴったりの食材。ブームとは関係なく、バックボーンにあるストーリーを含めてそのおいしさや楽しさを伝えていきたいですね。福井の方には身近すぎてわかってもらえない状況もありますが、地元の方にこそわかってほしいです」
百戦錬磨のシェフの言葉は、福井の料理人たちにどんな変化をもたらすのだろうか。
――つづく。
文:沼由美子 撮影:出地瑠以



















