


「伊勢」が紡ぐ大阪物語。
旅は終わらない。終わるはずだったのに、終わらない。だから、面白い。夢を見ているような夜を過ごし、あっという間に朝を迎える。再び「あば新」へ。夢じゃなかったことを確認して、気になる一軒の扉を開ける。そこには紛れもない大阪があった。
旅立ちの朝。
東京から青春18きっぷで途中下車しながらおもしろそうな店に飛び込みで入っていき、大阪の堺に着いたら真夜中に開く謎の天ぷら屋を調査――というミッションを終え、近くのホテルに入ったのは朝の4時過ぎだった。熱い湯をためてゆっくり風呂に入り、歯を磨きながら窓の外を見ると、冬の空が白み始めていた。

チェックアウトタイムの10時にロビーに集まると、編集担当の痛風エベも撮影担当のガリガリ君も寝不足と思えないほど晴れやかな顔をしていた。僕の顔もきっとそうだろう。四肢の疲労すら心地いい。夢のような旅だった。最初の1軒以外は全部出たとこ勝負だったが、行く店行く店すべてに心に響く物語があり、目を丸くするような偶然があった。すべてのタイミングが合って、唯一無二の旅になった手応えがあった。おそらくこんな旅はもうできないだろうな。いい映画が、キャスト、脚本、音楽、監督、すべてに奇跡の結合を見るように、不思議なぐらい、おもしろい旅だった。なんだか自画自賛みたいでサムいことを書いているなあと思うが、実際3人の口からは旅の賞賛しか出ないのだ。……ああ、やっぱりサムい図だなあ。
解散の前に、せっかく大阪に来たんだし、うどんを食べようとなった。昨日の魚市場によさそうなうどん屋があったのだ。ホテルの朝食は食べていたが、うどんなら入る。
ところが、深夜に明かりが灯って活気に満ちていた魚市場の店舗群は、朝の10時過ぎにはすっかり暗くなって静まりかえっていた。うどん屋も閉まっている。

天ぷら屋の「あば新」もシャッターが下りていたが、ちょうど“お母さん”ふたりが店からでてきたところに鉢合わせた。ふたりは僕らを見て「あれま」と破顔する。
「まだいらっしゃったんですね」
「片付けとかあるからこんな時間になるんよ」
時計を見ると10時半だ。
「いまから寝るんですか?」
「これから歯医者や。歯ぁ整理整頓せんとあかん」
整理整頓って。朝からまた笑ってしまった。すごいなあ、やっぱり。
「睡眠時間ってどれくらいなんですか?」
「毎日3、4時間やなぁ」
「ええっ」
昨晩(というか正確には今朝)の賑やかな店内が頭に浮かんだ。あの元気はどこからくるんだろう。ふたりともご高齢なのに。

「また来てやぁ」
お母さんたちのその声に「また来ます」と頭を下げながら、僕らは市場を後にした。
「じゃあ、さっきのとこに行きましょうか」
「そうですね」
ホテルから市場に向かう途上、気になる店があったのだ。南海本線堺駅の向かいだ。
見えてきた。
おっちゃんの唄。

なんと惹きつけられる店構えだろう。“18きっぷ食紀行”は昨晩(今朝)の「あば新」で終わっていたが、あらためて見るとこれはもう取材とか関係なく、寄らずに立ち去るなんてありえないと思った。
ドアを開けると、ヤッタ、やっぱり大当たりだ。琥珀色の木の店内に、ガス灯のような明かり、コーヒーの芳香が僕らを包んだ。カウンターの中には端整な顔立ちのママがふたりいる。

入口に大書されていたカレーライスが気になったが、まだお腹は減っていなかった。コーヒーだけ頼む。ママは豆を挽き始めた。
「お店、いつからやってるんですか?」
「昭和45年からやね」
僕とほぼ同い年だ。創業50年かぁ。
ママは二代目かな、と思ったが、創業者らしい。
「このカウンターすごいやろ。樹齢150年のけやきやで。当時で200万円や。後ろのテーブルも椅子も全部オーダーメードや。釘一個も使ってへん」

見た目からしてママは創業当時はまだ20代だろう。これだけの店がよく建てられたものだ。
「お父さんがトレーラー乗って、私は水商売してお金貯めたんや」
お金のかけ方にセンスがあるな、と僭越ながら思った。椅子もテーブルも、創業から50年経って、ますます人を魅了する色になっている。
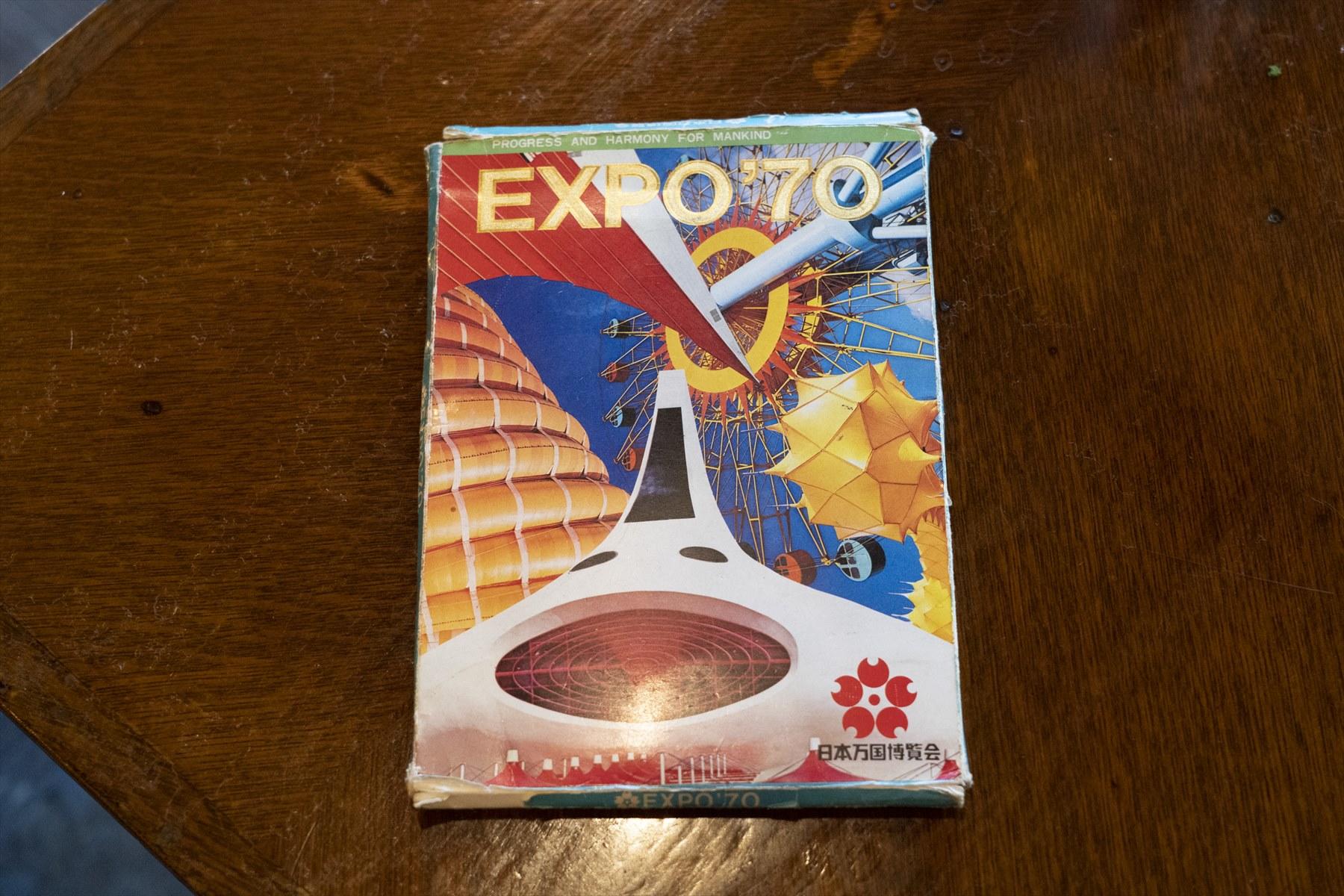
「兄ちゃんら、ええとこ来たわ」
カウンターでひとり、朝っぱらから水割りらしきグラスを傾けていた強面のおじさんが、振り返りながらそう言った後、「ガリガリ君」似のカメラマン阪本くんに目を留め、初対面の者への第一声とは思えない台詞を発した。

「あんただけ結婚してないやろ」
「なんでわかるんですかっ!」
冗談ばかり言うわりには人から冗談を言われるとまっすぐ返球するガリガリ君が、心底びっくりしたように問い返した。
おじさんはガハハハと笑い、一気に興に乗った。
「おっちゃん、何歳に見える?」

「65歳ぐらいですか」
「ええこと言うなぁ。82歳や」
「すごい!全然見えへんです」
「そやろ。おっちゃんは朝鮮人や。8歳でこっち来てん。冬でも裸足で半ズボンやった。あんたら戦争知らんやろ」
「知るわけないやろ」とママがおじさんにツッコミを入れた後、僕らのテーブルにコーヒーを置きながら、「このおっちゃんムチャ言いよるからな」と大げさに困った顔をして笑った。

「ここのママ、ふたりともべっぴんやろ。姉妹でやってるんや」とおじさん。やっぱりそうなんだ。似ていると思った。ママが言う。
「うちとこ女系やねん。女ばっか生まれて、この店も女6人でまわしてきてん」
僕ら3人は条件反射のように顔を見合わせた。まただ。みんな口を半開きにして、感心したような目つきになっている。この旅の最初の店、沼津の「中央亭」も女系で、7人の女性たちが店を切り盛りしていたのだ(現在は娘の旦那さんも手伝っているが)。
2軒にはもちろんなんの関係性もないから、この偶然にまったく意味はない。ただ、自由に旅をすると不思議なぐらいおかしな偶然が続く。縁が縁を呼ぶ人生の“あや”のように。あれはなんなんだろう?
「ほらほら、こっち」
声のする方を見ると、妹さんが頭に包丁を刺していた。

うむ……。同じ女系でも、沼津の「中央亭」とは趣がだいぶ異なるな。
――つづく。
 店舗情報
店舗情報
- 伊勢
-
- 【住所】大阪府堺市堺区竜神橋町2‐1‐23
- 【電話番号】072‐232‐6745
- 【営業時間】7:00~17:00、日曜は8:00~
- 【定休日】無休
- 【アクセス】南海本線「堺駅」より1分
文:石田ゆうすけ 写真:阪本勇










