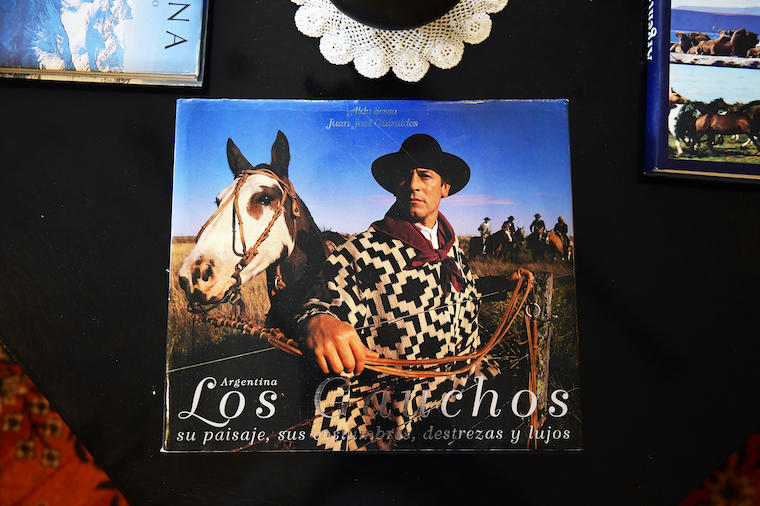


旅人たちを魅了するアルゼンチンの牛肉。
-
- 連載 : アルゼンチンを巡る冒険。
世界には牛肉が溢れている。霜降り牛に、乳飲み仔牛、そして昨今の熟成肉の流行は記憶に新しい。モー、牛自身もびっくりしているのではないだろうか。そんな中、地球を巡る旅人たちが「世界一!」と口を揃える牛肉がアルゼンチンにはあるという。
激論。肉が一番旨かった国は?
世界一周という途方もない冒険に、僕は悲壮な覚悟で出たのだが、いま思えばなんともバカバカしい。旅の初日から、泊まった宿で同じような世界一周トラベラーに会った。それからも行く先々で同様の輩に次々に会った。いくらでもいる。蜜蜂の大群ぐらいいる。世界一周は実にポピュラーなレジャーだった。

そんな旅人たちが集まり羽を休める宿が、世界各地にある。そこでよく語られるのが、世界で一番、というネタだ。
一番すごかった景色、人が一番よかった国、メシが一番旨かった国、エトセトラ。なまじっか世界をひととおり見てきた気になっているから、それぞれ一家言がある。意見は割れる。ただ、次の件に関しては、たいてい一致を見た――肉が一番旨かった国。
アルゼンチンだ。僕もまったく異論はない。特に南米にいた頃は、この話がよく持ち上がった。――アルゼンチンの牛肉って、なんかちょっとすごくない?
和牛のようなサシは入っていない、赤身の多い肉だ。でも不思議なくらい軟らかい。ジューシーで、肉の旨味が詰まっている。

僕は自転車旅行で、キャンプが多かったから、頻繁に自炊をしたのだけど、アルゼンチンではほとんど毎日と言っていいぐらい牛肉を食べた。旨いだけでなく、安いのだ。当時、グラムあたり60円ほどだったと思う。
海外ではごく一部の国を除いてスライス肉はない。アルゼンチンもステーキ用にカットされた肉か、塊でしか売っていない。だからステーキにすることが多かったが、変化をつけるために、牛丼なんかもよくつくった。
ナイフで薄く切って、醤油と砂糖で煮る。まな板も使わず、アーミーナイフでちぎるように切るから、薄くといってもせいぜい手の指ぐらいの厚さになる。牛丼にはまったく見えない厚さだが、軟らかいから簡単に噛み切れる。それでいて肉の味も濃い。

バーベキューは調理の形態ではない。文化だ。
なぜ旨いのか。それはやはりアルゼンチン人が無類の牛肉好きだからだろう。食への情熱が、牛の飼料や環境や品種、あらゆる面に神経を注がせている。
国民食ともいえる料理にアサードがある。いわばアルゼンチン風バーベキューだ。牛肉の塊を豪快に炭や薪で焼く。味付けは粗塩だけ。シンプルだからこそ、肉の質が問われる。
一戸建ての家には必ずといっていいほどアサード用の竈やパリージャと呼ばれるバーベキュー台があった。週末には、各家でアサードパーティーが開かれ、町のあちこちで煙が上がっている。その中を走ると、しょっちゅう声がかかった。
「おーい、肉食べていけよ」
遠慮なく飛び入りする。みんな笑顔で迎えてくれ、肉を切りわけてとってくれる。アサードはもはや食というより文化だ。

あるとき、山深い場所で、川にかかった橋を渡っていると、橋の下から「おーい」と声がかかった。見ると、中年男性がひとり、川原にいて、僕を呼んでいる。
「肉食ってけよ」
ほいきた、と自転車をとめ、橋の下に降りていくと、そこにはもうひとりの中年男しかいなかった。つまり、彼らはオッサンふたりだけで、肉と網を川原に持ち込み、アサードをやっていたのだ。そこまでして肉を焼きたいか!?

このようにアルゼンチンといえば、とにかく人々が“牛肉食い”で、生産量も世界4位という牛肉大国だ。そしてその肉の味は、世界中を旅する者たちをも魅了し、“世界一”とまで言わしめているのだが、じつは、個人的にはその牛肉以上に感動した肉がある。

――明日につづく。
文:石田ゆうすけ 写真:中田浩資/石田ゆうすけ









