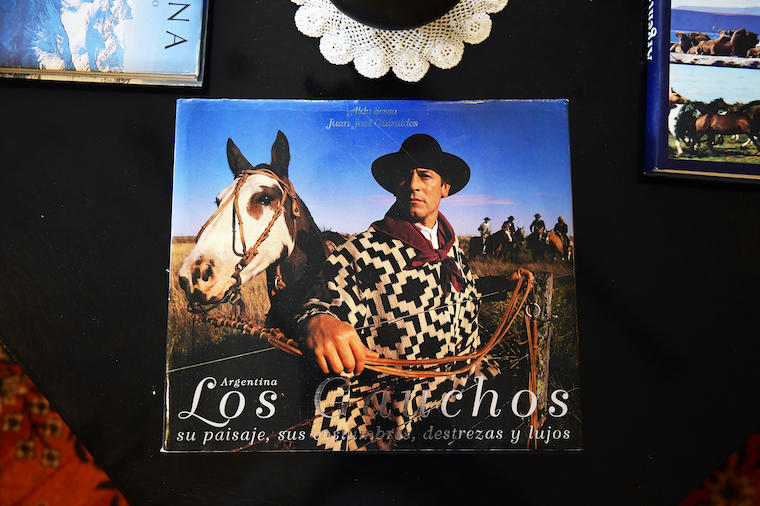


アルゼンチンの国民食「チョリパン」を食べたことはあるか?
-
- 連載 : アルゼンチンを巡る冒険。
肉の国アルゼンチンの国民的スナック、チョリパン。肉汁が溢れ出すチョリソーをカリッと焼いたパンで挟んで、お行儀は気にせず、かぶり付く。途端、脳内のリミッターが外れる。最後のひとかけを食べ尽くすまでもう止まらない。
アルゼンチン秘伝のチョリソ。
「日本にはまだない食べもの」
「チョリソとパンの組み合わせが秀逸」
「名前がキャッチー」
「アルゼンチンが好き」
こういった理由から、チョリパンの店を東京に出そうと思った中尾さん夫妻。世界一周の旅から帰ってしばらく日本で過ごした後、修業のために再びアルゼンチンを訪れた。

首都ブエノスアイレスには、チョリパン屋がずらりと並んでいるエリアがある。毎日そこに通ってしらみつぶしに試食し、そのなかの1軒に弟子入りを頼んだ。
「味がよかったのもありますが、恐そうなオヤジばかりのチョリパン屋のなかで、その店の店主がいちばん話しかけやすかったんです」と中尾真也さんは笑う。

滞在可能期間の3ヶ月をめいっぱい使って、修業させてもらったのだが、どの店もそうであるように、肝心のチョリソが自前ではなかった。そこで配達のお兄さんをつかまえて頼み込み、チョリソ工場の場所を突き止めた。
工場でも頭を下げ、つくり方を教えてほしいと頼んでみたのだが、「ダメダメ」とにべもなかった。中尾さんはすっぽんのように食らいついた。
毎日早朝から工場に通い、暗くなるまで彼らの目に入るところでウロチョロした。そのうち工場の人たちも笑顔で接してくれるようになり、3週間かかってようやくレシピを聞くことができたのだ。

「豚のタンを入れて食感を出したりしています。ただ日本の食材だと、ねかせるタイミングやスパイスの分量が現地と同じようにはいかなくて、いろいろ試しながら工夫していきました。味がしっくりくるまで5年くらいかかりましたね」
中尾さんはほぼ毎日、店でチョリソを仕込んでいる。材料を腸詰めにしてから2~3日冷蔵庫でねかせ、その後、炭で半生状態まで焼き、1日おいて使用するという。
「炭で焼くことで熟成が進んで、より旨味が増すんです」

飢えた鮫のようにかぶりつく。
注文すると、中尾さんはチョリソを半分にカットし、焼き始めた。フライパンを包むほどの強火だ。チョリソから染み出た脂に火が移り、フランベのように炎が上がった。


同時にパンも焼く。こっちは炭を使う。アルゼンチン式バーベキューの「アサード」同様、ごつい金網の下で炭をおこし、その上に全粒粉パンをのせる。
「余分な水分が抜けて表面がカリッとします。炭の香りはアルゼンチンの味の要なので」

わざわざ炭をおこすわけだから、かなり手間だと思うが、現地のチョリパン屋の味を忠実に再現しようとしているのだ。
焼けたパンにチョリソをのせ、チミチュリ――酢と油にオレガノ、唐辛子、パプリカなどを入れたソース――をかけて完成。

かぶりつくと、香ばしいパンの皮がパリパリ砕けて全粒粉のふっくらとした甘味が口内に広がり、次いで、こんがり焼けたチョリソの表面に歯がガリッと刺さる。噛み砕くと、粗挽きの牛肉ミンチが弾けるようにあふれだす。同時に、チミチュリの酸味および辛味が広がり、唾液が大量に分泌された。うはは、これだよこれ。僕はテンションが一気に上がり、飢えた鮫のようにバクバクかぶりついた。同行していた編集者の“しゃべらなければイケメン”大治朗くんは初めての味に目を丸くしている。腸詰をはさんだパンだからホットドッグだろう、なんて思っていた君ぃ、ザクとは違うんだよ、ザクとは。


“国民食”には人口に膾炙するだけの理由がちゃんとある。世界を旅しながら、各国のスナックを食べるたびにそう思ったものだが、チョリパンほど説得力のある料理はなかなかないかもしれない。伍するのはメキシコのタコスぐらいかな。パッと思いつくものでは。
「アルゼンチン人のお客さんもよく来ますよ。『日本でこの味が食べられるなんて』とウルウルした目で語ってくれた人もいましたね。訊けば、3年帰っていないって」
いまでも中尾さんたちはアルゼンチンに足を運び、現地の味を確かめ、チミチュリの材料を仕入れてくるという。

「ちゃんとしたものをつくらないと、と思うんです。日本ではほとんどの人がチョリパンを知らないわけですから、自分たちには責任があります。ウチのを食べてアルゼンチンの食の印象を決める人もいますから」
なるほどなあ。「ほとんどの人が知らないから」という同じ理由で、「手を抜ける」と考える人は少なくないと思う。でも模倣には、“厚み”がない。本物にこそ文化が備わっているからだ。文化とは長年かけて磨かれ、定着したものだ。
中尾さんのように他国の食の成り立ちを理解し、リスペクトしている人がつくるから、人の心を打つんだろうな。

――つづく。
 店舗情報
店舗情報
- ミ・チョリパン
-
- 【住所】東京都渋谷区上原2-4-8
- 【電話番号】03-5790-9300
- 【営業時間】11:00~22:00
- 【定休日】火曜 第2、第4月曜(祝日の場合は営業)
- 【アクセス】小田急線「代々木上原駅」より7分
文:石田ゆうすけ 写真:中田浩資










