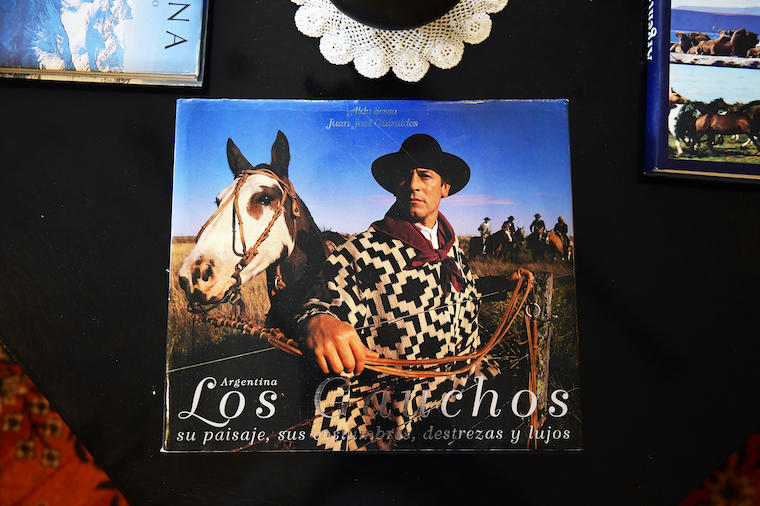


アルゼンチン人を虜にする「エルカミニート」のエンパナーダ。
-
- 連載 : アルゼンチンを巡る冒険。
アルゼンチン流のミートパイ"エンパナーダ”。サクサクのパイ生地の中には、肉がぎっしり。東京は赤羽橋の「エルカミニート」には、アルゼンチン人がレシピを懇願するほどの逸品があるという。
数多くの国のミートパイのなかでも出色だった。
パイ生地で具材の肉を包んだミートパイは多くの国で食べられている。サンドイッチと並ぶ軽食といっていいかもしれない。
中南米ではエンパナーダと呼ばれ、路上の屋台で日常的に目にするほか、パーティーでも必ずといっていいほど出される定番中の定番だ。

中の具は様々で、国や地域によって特色がある。
旅人から「世界一肉の旨い国」と支持され、国民も「俺たちの主食は肉だ」と公言してはばからないアルゼンチンのエンパナーダは、やっぱり肉の存在感が圧倒的で、僕が食べた数多くの国のミートパイのなかでも出色だった。
「そのエンパナーダが抜群に旨い店が日本にもあるらしいです!!」
喋らなければイケメンの編集担当、大治朗くんからそんな話を聞いて向かった先が、東京タワーの近くにあるアルゼンチンレストラン「エルカミニート」だ。

シェフの浅井敬三氏はホテルオークラ等でフランス料理の修業をした後、アルゼンチンの日本大使館で4年間料理を担当した人だ。任期を終えた後、6年間南米各地に滞在し、食べ歩きをしたらしい。
どこの料理が一番でしたか、と訊くと、「そりゃアルゼンチンだよ~」と即答が返ってきた。まあ、店を出すくらいだから当然か。
「じゃあアルゼンチン料理のどういうところが印象的でしたか?」
「そりゃやっぱり肉とワインだよ~」
浅井シェフはどこか楽しそうな表情で言う。
前回、訪ねたチョリパン店の中尾さんもそうだし、たぶん僕もそうなのだが、旨い肉について語るとき、人はどうして獣のように目がギラリと光るのだろうか。

メニューを開くと、うれしいことにマルベックのハウスワインがあった。グラスで出している店はなかなかないから、これは貴重だ。
マルベックはアルゼンチンワインの代名詞といった品種だ。ブラックベリーを思わせる濃厚な果実味と、強くまろやかなタンニンが特徴の、黒みがかった赤ワインで、肉によく合うのだ。それとエンパナーダを頼む。

アルゼンチン人がレシピを教わりに来る味。
オーブンで焼きあげられたエンパナーダはふたつも食べれば腹が満たされそうなほど大きかった。
「真ん中をナイフでふたつに切って、切り口からかぶりつくのがいいですよ」とサービスを担当してくれたマダムが言う。
この店はレストランだけにナイフとフォークがついてくるが、エンパナーダはもともとスナックだから手で食べるのが基本だ。

言われた通り、ナイフでふたつに切った後、手に持ってかぶりついてみる。
マダムは正しかった。切らずにかぶりついていたら、パイから飛び出してきた具で舌が火傷したんじゃないだろうか。それぐらい熱い。パイで包むのは味や香りのためだけでなく、料理を冷まさないためでもあるんだろうな。
それを真ん中から切ることで、熱を適度に逃がす。味がクリアになる。パイ皮のサクサクした歯触りと、思わず目を細めたくなるような小麦粉の焼けた香ばしさ、その中からあふれ出る粗挽きの牛肉と玉ねぎのコク、それにこの甘味は……レーズンだ!
さらにはゆで卵にオリーブの実、ああ、なんてボリュームのある旨さだろう。あちあち、はふはふ、と口の中で具材を転がしながら咀嚼してワインを含み、濃縮した果実味と具材との混淆にうっとりしつつ、再びミートパイを頬張り、あちあち、はふはふ、またワインを含んで、広がる広がる、か~っ、たまんねえ!
うーん、これは“海外旅行あるある”かもしれない。その国の料理なのに、現地で食べるより、帰国後、日本で食べたほうがおいしかった、というあれだ。
「やっぱり食べものは日本が一番」と多くの旅行者が口にする意見に、僕はあまり共感しないのだが、料理によっては確かに、日本人のシェフが微に入り細を穿って手をかけたもののほうが、現地のものより繊細で洗練されているというケースは少なからずある。このエンパナーダはまさにそうだった(もちろん、僕個人の経験と印象の話なので、さらに上等なエンパナーダが現地にあるかもしれないが)。


アルゼンチン出身のJリーガー、エスクデーロ選手と彼の両親(父親も元Jリーガーで、引退後、日本でコーチを歴任)もよく店に来るらしい。
8年前に韓国のKリーグに移籍することになり(現在はJリーグに復帰)、家族全員で韓国に引っ越すことが決まったときは、アルゼンチン人のお母さんがエンパナーダのレシピを浅井シェフに教わりにきたらしい。わかるなあ。

店内に流れるフォルクローレに、タンゴショーが始まりそうなムーディーな照明、マルベックの深みのあるエレガントな味わいに、エンパナーダを始めとするアルゼンチン料理の数々。
地球の裏側、アルゼンチンは気軽に行ける場所ではないけれど、行った気分で本物の味を楽しめる場所は、幸運にしてあるのだ。

ーーつづく。
 店舗情報
店舗情報
- El Caminito
-
- 【住所】東京都港区東麻布1‐12‐11
- 【電話番号】03‐3582‐9380
- 【営業時間】18:00~21:30(L.O.)
- 【定休日】日曜、祝日
- 【アクセス】都営大江戸線「赤羽橋」より5分
文:石田ゆうすけ 写真:中田浩資














