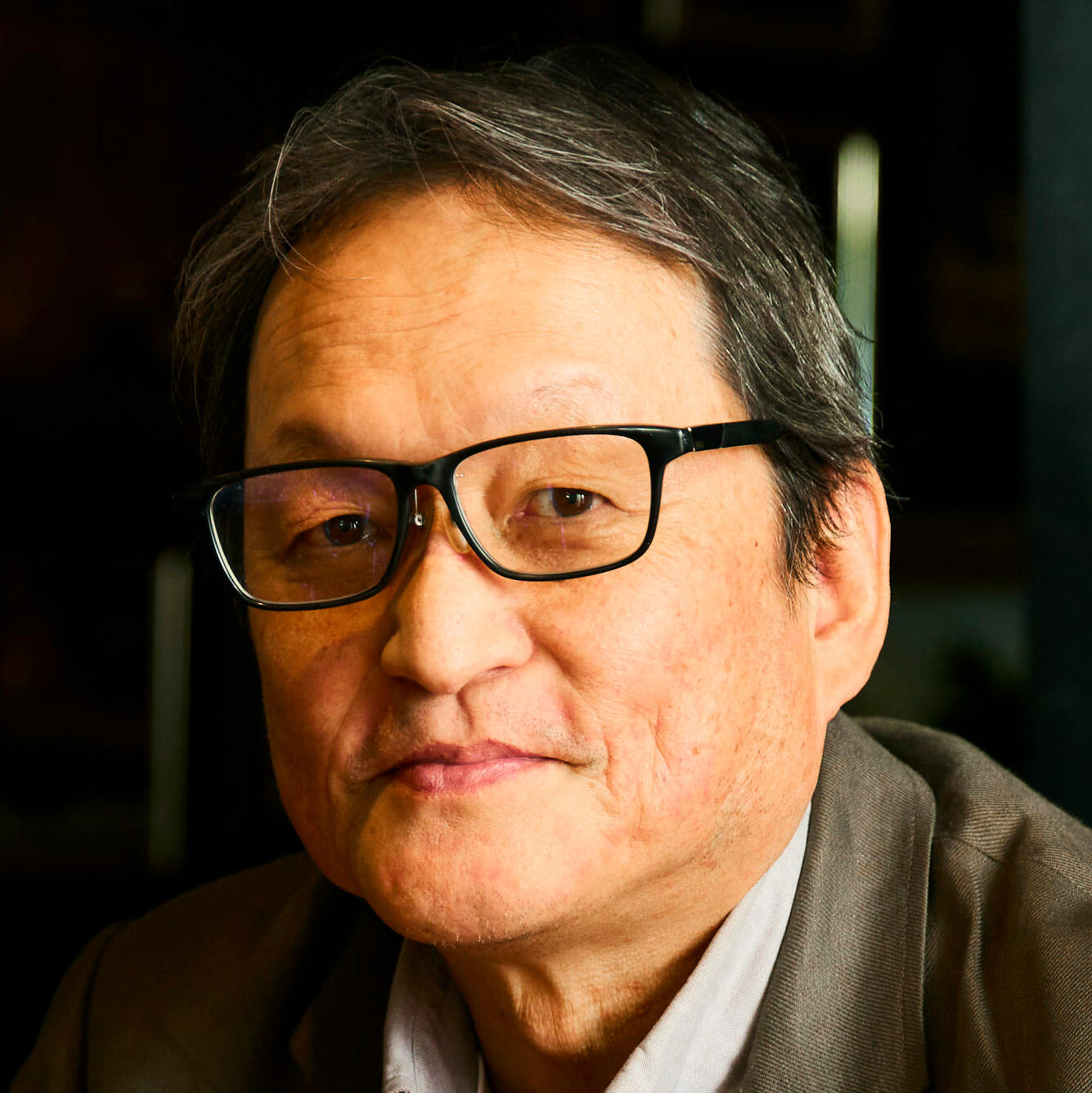お客様から励ましの言葉をいただく。それが5年後、10年後の店の将来にとって大事なことなのだと痛感しました──有楽町「バーデン バーデン」
有楽町のガード下。本格ドイツ料理が自慢の大箱ビアレストランも、長い休業を余儀なくされている──かつてない苦境に立たされる酒場の人たちは、どのような思いでこの日々を乗り越えてきたのか。さまざまな店への取材を通して、「酒場の良さってなんだろう?」とじっくり考えていくルポルタージュ連載。第八回は、コロナ禍で飲食店のあり方を見つめ直したという、店主のリアルな声を伺いました。
酒場が酒を提供できない状況が続いています。9月末をもって緊急事態宣言が解除されることが期待されますが、飲食店にはまだ、さまざまな不安もあることでしょう。解除後の感染対策はこれまでどおりでいいのか。そもそも、酒場が営業を中断している間に感染者は急増したり急減したりしたことは、酒場の営業自粛とどのような因果関係があったのか。疑問も少なくないからです。
なにより、酒類提供自粛の要請によって多くの酒場は休業に追い込まれ、客とのつながりが途絶えています。酒場にとってもっとも大事なものをどう修復するのか。あるいは、その先に、どのような展望を開くことができるのか。今回は、酒場が置かれた現状について忌憚のないところを、創業41年のドイツレストラン「バーデン バーデン」にお伺いいたします。

月の固定費は1000万円ほど。営業自粛で売上がゼロになりました
有楽町のJR高架下。明治時代に建造された風格あるアーチ型の橋脚の壁面は古びたレンガだ。そのアーチを店のファサードにしているのが、ドイツレストラン「バーデン バーデン」です。1980年にオープンし、現在は創業者の息子さんである曽根崎武吉さんが経営をしています。
「もとは、証券マンだった父が開いた店です。ドイツを旅したときにビールと料理の魅力に目覚めて開業したと、父は昔の従業員に語ったそうですが、母に言わせると開業前にドイツに行ったことはない(笑)。それでも、店を始めてからは何度もドイツへ足を運び、本場の料理とビールを見て回ってホフブロイというビール会社と契約し、それは現在まで続いています」

曽根崎さん自身は高校大学とボクシングに打ち込み、社会に出てからはサラリーマンを経て千葉県の高校教員として過ごしてきましたが、2015年、この店の経営者になる。現在で6年目。このうちの1年半はコロナとの闘いでした。曽根崎さんと奥様の和美さんが役員で、社員は9名、そのほかアルバイトも雇ってきた。店の席数は120に及びます。
「昨年の4月、5月の営業自粛のとき痛感したのは、家賃や人件費の大きさです。うちくらいの規模だと、諸々の経費をプラスすると、月の固定費は1000万円ほどですが、営業自粛で売上がゼロになりました。このとき考えたのは、営業をしてもしなくても家賃はかかるということです。だから、それまでは週末は16時、平日は17時オープンだったのを、土日祝日は昼の12時から開けて、ランチや昼飲みのお客様を取り込もうとしました」
週末には、曽根崎さんはレーダーホーゼンという革製のパンツ、奥様の和美さんはディアンドルという、いずれもドイツの民族衣装を身に着けて、店に出ていた。
「緊急事態宣言が明けてからは営業時間の制限がなかったんですね。それで、深夜営業することにしました。警察に届け出をして、私と妻とふたりだけ残ってソーセージを焼いたものなどの簡単な料理とビールで営業をしたんです。やってみると金曜日の晩などはお客様もそこそこに入り、売上が落ちる月曜の分をカバーできた。私と妻のふたりだけでできる範囲でしたが、最初の頃は、朝5時までやってました(笑)」

飲食店に向けた感染対策として、国土交通省から道路占用許可基準の緩和措置が行われたときも、店の前の道路にテーブルを出す許可をさっそく申請する。もちろん、営業自粛への協力金、持続化給付金、雇用調整助成金など各種の申請のほか、緊急の融資など、この事態を乗り切るためのあらゆる方策を模索した。店を守るために必要なことは、なんでもやる。「バーデンバーデン」には、そうする以外に道はなかった。
緊急事態宣言が突然決まり、生ビールを大量廃棄することに
経営者となった2015年からの5年間に、曽根崎さんがドイツを訪ねたのは6度に及ぶといいます。
「私はこの仕事に就く前まで教員ですから、まったくの素人。とにかくドイツを知らないといけない。それで毎年のように出かけて勉強をしました。その都度、シェフはもとよりスタッフも交代で連れて行って、一緒にドイツを体験し、リアルなドイツの味を表現できるか、模索してきました。以前ドイツに勤務されていた方に懐かしいと言ってもらったり、たまたま店の前を通りがかったドイツ人のお客様から、店の前に掲げている“マリエンプラッツ”というミュンヘンの地下鉄駅の名前のプレートを珍しいと声をかけてもらって、それが縁で後にミュンヘンへ行ったときに一緒に飲んだこともあります」

先代が契約を結んだホフブロイは、400年もの伝統を誇るドイツビール。それを直接輸入して、アイスバイン(塩漬け豚すね肉の煮込み)やジャーマンポテトなどの料理は本場さながらの味とボリュームで楽しませる。それが「バーデン バーデン」流。先代が店を始めたときはビアホールだったと曽根崎さんは謙遜するが、現在では正当なドイツレストランであり、居酒屋なのです。
「この界隈は歌舞伎座、帝国劇場、東京宝塚劇場、日生劇場など劇場も多いですし、父が歌舞伎役者や舞台俳優の方々が大好きだったから、よくお店にも来ていただいているんですよ。『レ・ミゼラブル』公演の打ち上げを貸し切りでやっていただいたことがあるんですが、そのときは俳優の方々が大合唱してくださった。貴重な経験でしたね。父のつくってくれたつながりです」
有楽町の高架下に本場ドイツのお祭り騒ぎのような酒場風景が繰り広げられる。それが、1年半前までの「バーデン バーデン」だった。しかし、長引くコロナ禍に、店も翻弄されたのです。今年1月から2度目の緊急事態宣言。4月下旬からは3度目が発出された。
「当店ではドイツから直輸入した生ビールを、お台場の冷蔵倉庫に常時100~400樽ほど保管してあるんです。それをゴールデンウィークの連休用に、倉庫からいつもより多く店内へ移しておいたのですが、緊急事態宣言の再発出が急遽決まったために倉庫へ戻すことができなかった。店の冷蔵庫に保管できるのは15樽(450リットル)くらいで、残りは店内に置いておきます。通常であれば常温保存でも劣化しないのですが、この5月、異様に暑い日もあったんです。それで、試飲してみたのですが、ほんのちょっとでも違うなと思ったものは、やはりお出しできない。もったいないとは思いますが、本当においしいドイツビールを目当てにうちの店に来てくださるお客様に対して、絶対に裏切ることはできないですから。結局のところ、1樽(30リットル)を35樽、計1トン以上の生ビールを廃棄することになりました。これは私のミスですが、緊急事態宣言が出ることが、もう少し早くわかっていればとも思いますね」

営業ができないだけでなく、仕入れてしまった商材を廃棄しなくてはならない。まさに正念場です。ドイツの惣菜の通信販売を始めてはいるが、平常時の通常営業の1%ほどの売り上げにしかならないという。この夏から現在につづく緊急事態宣言に入ったときには、ドイツビールも、ドイツワインも出さず、ドイツ料理だけで勝負しようと、店を開けてみたこともある。やれることはなんでもやるという心構えだった。しかし、1日で断念することになったのです。
「近くには、お酒を出す店もあるんです。お客様がそちらに流れると、こちらは閑古鳥状態で、店を開けただけロスが出てしまう。それで、すぐに諦めて、酒類提供自粛の間は店を閉めることにしたのです」
酒なしで、酒場は成り立たない。カレーを出せないカレー専門店が成り立たないように。

しかし店は経営しなければならない。曽根崎さんはかねてより堅実な経営を心掛け、内部留保の蓄積に努めてきた。それが、コロナ禍にあって大いに役立っているといいます。
「コロナ以前から、しっかり利益を計上した決算ができていたので、私たちなりには大きな融資を受けることができました。ほぼ利息のない融資です。それに加えて協力金もあるので、毎月赤字にはなるもののなんとか回せています」
さらに曽根崎さんには、希望につながることがあった。6月下旬、いったん緊急事態宣言が解除されたときのことです。
「7月の緊急事態宣言発出までの3週間ほどの間に、多くのお客様にご来店いただき、励ましの言葉をいただきました。妻の手を握って涙をこぼした方もいる。みなさんが、この店のことを本当に親身になって心配してくださっていたんです。感染対策も目先の利益も大切ですが、それよりも、こうして励ましの言葉をいただくことが、5年後、10年後の店の将来にとって大事なことだと痛感しました。店を開けたり休業したりを繰り返してきて、気づいたのは、こういう状況の中で、新規のお客様がリピーターになったり、顔なじみが常連様になったり、以前からの常連様は、家族みたいになって、親身に心配してくれるということです」

曽根崎さんの頭には、いろいろな顔が浮かぶ。この店を夢の国、ディズニーランドにたとえた若いお客さん。時短営業中、ぎりぎりの時間になっても駆けつけて必ず2リットルのビールを飲んで帰る女性のお客さん。そして、親身になってくれる常連客の、顔の数々が、浮かぶのです。
「コロナ禍で、飲食店としてのあり方を考えさせられた。いや、見つめなおしたと言いますか。おいしい料理とおいしいビールを出し、きめ細かなサービスをすることは、実は最低限のことです。お客様と心と心で会話をする。そうした、うわべだけじゃない本当の信頼関係をいかにしてつくっていくか。ここが、星の数ほどある飲食店の中で生き残っていくために一番大切なことだと、お客様から励ましの言葉をいただくたびに感じているところです」

*緊急事態宣言中は休業。最新の情報は店のHPにて確認を。
 店舗情報
店舗情報
- バーデン バーデン
-
- 【住所】東京都千代田区有楽町2‐1‐8 JR高架下
- 【電話番号】03‐3508‐2807
- 【営業時間】17:00~22:30(L.O.) 土曜は12:00~22:30(L.O.) 日曜は12:00~21:30(L.O.)
- 【定休日】無休
- 【アクセス】JRほか「有楽町駅」より徒歩3分
文:大竹聡 写真:衛藤キヨコ