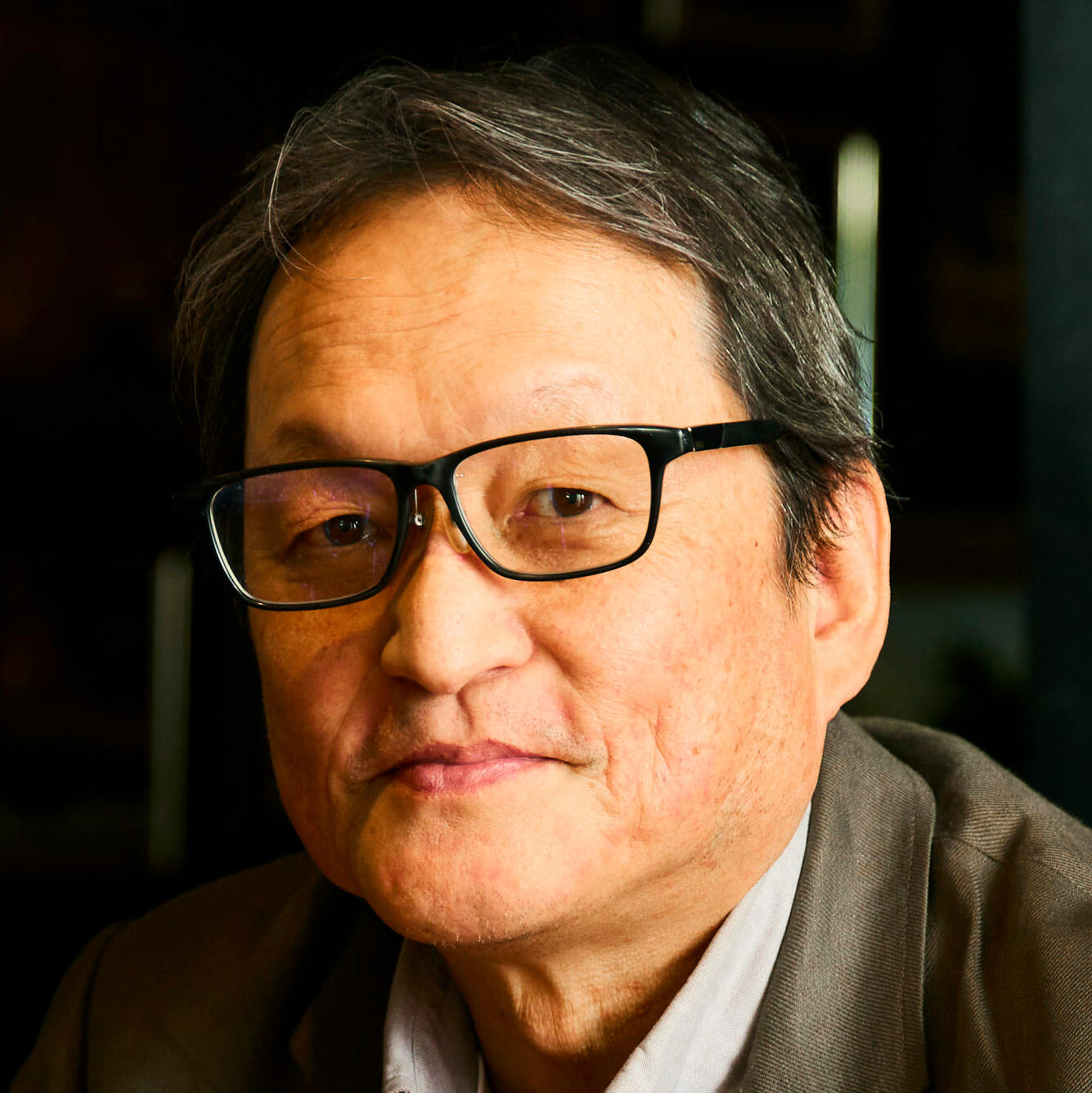この店はなくしちゃいけない。こんなことで負けてはいられない──浜松町「秋田屋」
浜松町に「秋田屋」あり。街のランドマークとして長年愛されるもつ焼き屋にも、酒の提供ができない日々が続いた──かつてない苦境に立たされる酒場の人たちは、どのような思いでこの日々を乗り越えてきたのか。さまざまな店への取材を通して、「酒場の良さってなんだろう?」とじっくり考えていくルポルタージュ連載。第二十一回は、90年以上の歴史を持つ老舗の三代目に、店への思い、街への思い、そして酒場への思いをじっくり伺いました。
2021年は酒場にとって、受難の1年でした。酒の提供自粛を要請された期間は4ヶ月半を超え、その他の期間は大幅な営業時間の短縮が要請された。酒類提供解禁に加え、時短要請も解除されたのは10月25日のこと。そのときにはもう、秋も深まっていたのです。
かつて経験したことのない1年を過ごし、酒場は今、難しい局面に立たされている。新たな変異株の蔓延が今も懸念される中、客足は以前のようには戻っていない。ようやく小康を得たものの、世の中全体から見たときに非常事態はまだ続いている。そんな現実に直面している酒場が、2年弱のコロナ禍を経て何を経験したのか。営業再開から2ヶ月が経過した今、どんなことを考え、先行きをどのように見据えているのか。今回は、昭和4年創業の「秋田屋」さんをお訪ねし、三代目の金沢義久さんにお話しを伺いました。

街が普通に戻らないと、人も戻ってこない
2021年12月16日午後3時半。開店と同時に、表に並んでいたお客さんが店内に入ってきました。その少し前まで店内の一角で金沢さんからお話を伺っていた取材チームは、その日の最初のお客さんたちを迎える形になりました。次々に客は来る。みるみるうちに、席が埋まり始め、2階にも上がっていく。この光景をただ眺めただけなら、昔ながらの秋田屋の開店風景だよねと納得するところですが、2020年4月の、最初の緊急事態宣言発出の際には、こうではなかったのです。金沢さんが振り返ります。
「街中に人がいなくなりましたね。時間短縮で営業することはできましたが、人がいないのではやっても無駄だと思い、休業にしました。それから手造りでパーテーションを作り、煮込みの通信販売を思いついて、真空パック機をレンタルして試作品を作りました。ところが、煮込みは汁ものなので真空にするのが難しい。でも、いったん煮込みを冷凍してから真空パックにすれば通信販売できることがわかりました」

「こうして商品そのものはできたのですが、今度は売り方がわからない。ホームページを立ち上げたのはいいのですが、検索してもらうにはどうしたらいいのか。そこで考えたのが裏メニューです。5月に街の人の流れも少しだけ戻ってきたので時短で営業を再開し、店内に、ホームページのアドレスとQRコードを掲示して、ここを見てくれた方だけ注文できますよ、という感じで、定期的に出すようにしました」


秋田屋があるのは浜松町。東京モノレールの始発駅で、向かう先は羽田空港である。出張や観光の行き帰りの途中、秋田屋で一杯やってから羽田に向かったり、旅先から帰ってきたその足で秋田屋へ寄ったり、多くの旅人に愛されてきた。それゆえに、秋田屋を知る人は、東京近郊だけでなく、全国に広がっている。
「うちの味を知ってくれているお客さんが、通販で買えるとわかって、全国から注文がくるといいなと思いました」
その思いは届き、現在では各地からの注文も入り、この年末の注文も増えているという。

街から人が消えたそのとき、もうひとつ金沢さんが急いだことがあった。
「うちでは14人が働いています。営業ができないと、人件費がたいへんなことになります。だからまず、国金(現在の日本政策金融公庫)さんに、とりあえず借りられるだけ借りようと思いました。行政からの協力金や雇用調整助成金もあって、結果的にはひとりも辞めることなく、やってこられましたが、当初はやはり資金が必要でした。助成金にしても申請してから支払われるまでには2ヶ月くらいかかりましたから、その分の体力がないと続きません。金策も、結構たいへんでしたよ」
金沢さんの口調はとても穏やかだが、すべてが初めての体験だ。実際のところ、昭和4年創業の老舗にとっても、コロナ禍でのかじ取りは困難を極めたと想像がつきます。


「店をなんとか開けてみると、それなりにはお客様に来ていただけた。最低ラインの人数くらい。当然売上は足りないので、その分を埋めるために、煮込みの味付けを少しだけ変えてご飯にのせた煮込み丼を、昼だけ、テイクアウトで出しました」
秋田屋の開店は以前から午後3時半だが、時短要請のため閉店時刻が早まっていた。それを補うために昼のテイクアウトに踏み切ったのだ。それでも、街全体に、以前ほどの人の流れは戻らない。客も何割かは少ない。
「しかし、こればかりは、しょうがない」
金沢さんはそう割り切った。逆に切らさないようにしたのは、気持ち。
「街が普通に戻らないと、人も戻ってこないだろう。そういう考え方でいくしかない」


そんな秋田屋に降りかかったのが、2021年4月からの新たな要請だ。コロナ禍に入って1年、なんとかやりくりをしてきたのに、今度は酒の提供自粛要請が発令された。
「お酒を売っちゃいけないというのは、営業しちゃいかん、ということ。お酒あってのつまみですからね。これはもう死刑宣告みたいな感じでした。それでも何かしなくてはと思い、もつ焼きと煮込みのテイクアウトと通信販売をしました。従業員には3人くらいずつ順番で出てきてもらって、これだけは続けてきたんですね」
この地道な仕事を、周囲の人たちが見ていたのです。
「日ごろ、うちの店には入りづらいと思っていたご近所の主婦が、テイクアウトできることを知って買いに来てくれた。もちろん常連のお客さんにも来ていただけましたし、がんばってくださいね、続けてくださいねと、声をかけてもらうこともありました」
事実、取材当日も、ベビーカーを押した若い女性が、テイクアウトを買いにやってきていた。店の周辺はオフィスビルが多いが、JRの線路を超えるとタワーマンションがあり、学校もある。この街に住む人々にとって、秋田屋のテイクアウトは、新たな食の楽しみになったのかもしれない。少なくとも、客層という点では広がったことは間違いない。

やっと仕事ができる、身体を動かせる。それが一番嬉しかった
現在の店は1、2階合わせて54席。混みあうときの賑やかさと、もつ焼きの香りは、浜松町の名物だ。戦前に麻布十番の近くで店を始めたのが秋田出身の先々代で、この店の創業者だ。金沢さんのお祖父さんにあたる。戦後は新橋で短期間店をやり、その後、浜松町に来た。今年59歳になる金沢さんは、前回の東京オリンピックの直前に生まれ、子供時代は東京タワーが庭のようなものだったという。
「祖父は秋田の横手の出身で、『高清水』が好きで、東京で売りたいというところから店を始めたそうです」


夕刻、浜松町駅から大門へ向けて歩いてくると、「高清水 秋田屋」の袖看板の右奥に、赤く美しい東京タワーが見える。秋田屋は、東京タワーと同様に、浜松町のランドマークなのだ。酒を出せない長い夏を過ごしながら、金沢さんは、この一時が辛抱なんだと考え、従業員にも声をかけたという。
「今はちょっと我慢だよね。みんなでなんとか乗り切ろうよ」
そんな金沢さんの胸には、老舗の三代目としての、強い思いがあった。
「この店はなくしちゃいけない。こんなことで負けてはいられないという気持ちでした」

昭和6年生まれの先代は子供時代とはいえ戦争を知っている。良い時も悪い時も、知っている。そんな先代は、金沢さんに、こう言い聞かせてきたという。
「とにかく真面目な商売をしなさいと教えられました。真面目にやっていれば、なんとかなる。自分の目が届く範囲で、真面目に商売をしなさいと」
その教えを胸に、辛抱の夏が過ぎ、秋になった。いよいよ10月1日。緊急事態宣言が解除された。

「やっと仕事ができる。身体を動かせるというのが、やっぱり一番嬉しかったですね。それまでテイクアウトを販売しているだけでしたからね。お客さんと話しながら商売できるのは、やっぱり全然違います。お客さんと言葉のやり取りをしているのが面白いし、楽しい。やっと、それをできるんだと思いました。お客さんも、ああ、開けてくれたんだねって喜んでくれて、店がとても華やいだ感じでした。ずっと来てくれていたお客さんがまた戻ってきてくれたのが、なにより嬉しかったです」

取材に伺った2021年12月中旬現在、お客さんの入りは従来の7~8割まで回復しているということです。コロナ禍を経験した今、思うのはどのようなことでしょう。
「来てくれたお客さんがおいしいって言ってくれれば、我々、それが一番嬉しい。うちの場合、これからも味を変えないのがいいかなって思っています。もつ焼き、煮込み、たたき(肉団子)、氷頭なます、お新香、くさや、それから季節のものなど、いろいろですが、どれも味を変えない。たとえば、煮込みが、相変わらずうまいよって言っていただけること。それでいいんだろうなって、思っています」
秋田屋の創業は西暦では1929年。店の歴史は2022年で、丸93年になる。あと7年で1世紀だ。そんな店の灯りが、今日も浜松町の通りを照らしているのです。そこには変わらぬ光景があり、変わらぬ味がある。それが、我等酒好きを日々吸い寄せる。こんな酒場を守りたいという切実な思いは、店ばかりでなく、客のものでもあるようです。

*最新の営業時間など、詳しくは電話やHPで確認を。
 店舗情報
店舗情報
- 秋田屋
-
- 【住所】東京都港区浜松町2‐1‐2
- 【電話番号】03‐3432‐0020
- 【営業時間】15:30~21:00(L.O.)土曜は~20:00(L.O.)
- 【定休日】日曜 祝日 第3土曜日
- 【アクセス】JR・東京モノレール「浜松町駅」より2分、都営地地下鉄「大門駅」より1分
文:大竹 聡 写真:衛藤キヨコ