


賭けなければ当たらない。
-
- 連載 : 山の音
賭け事は、参加した瞬間に的中の権利を得るとともに、その逆の可能性もまた孕むもの。つまり、賭けなければ外れません、ということでもある。けれども、多くの人が魅了されるのは、自らの智慧だけではどうにもならない何かが介在することによって、未来が劇的に変わることへの期待感があるから。なんて言ったら、綺麗事過ぎるかな。その何かは、運と呼ばれたりするもんね。あれ、これって、なんだか、人生と似ている。
ギャンブル、というほどのものでもない
街を歩いていてふと宝くじ売り場が目に留まり、10枚1組の連番を購入することが年に2、3度ある。特に1等に当たることを期待するでもなく、抽選の日をドキドキしながら待つわけでもない。なんというか、お守りのような感じで、そのくじを、いつも使っているリュックサックの内ポケットに入れておくのが好きなのだ。
そしてまた偶然通りかかった宝くじ売り場で、当選番号を確かめる。夏の初めに購入したサマージャンボ、昨日、調べてみたら5等が当たっていた。6等と併せて3,300円の払い戻しである。3,000円で買ったので300円の儲けである。ギャンブル、というほどのものでもない。本気でギャンブルに賭けている人間の顔というものは、一生懸命に働いている人の顔、というのとは少し違った刹那的な色気がありますね。
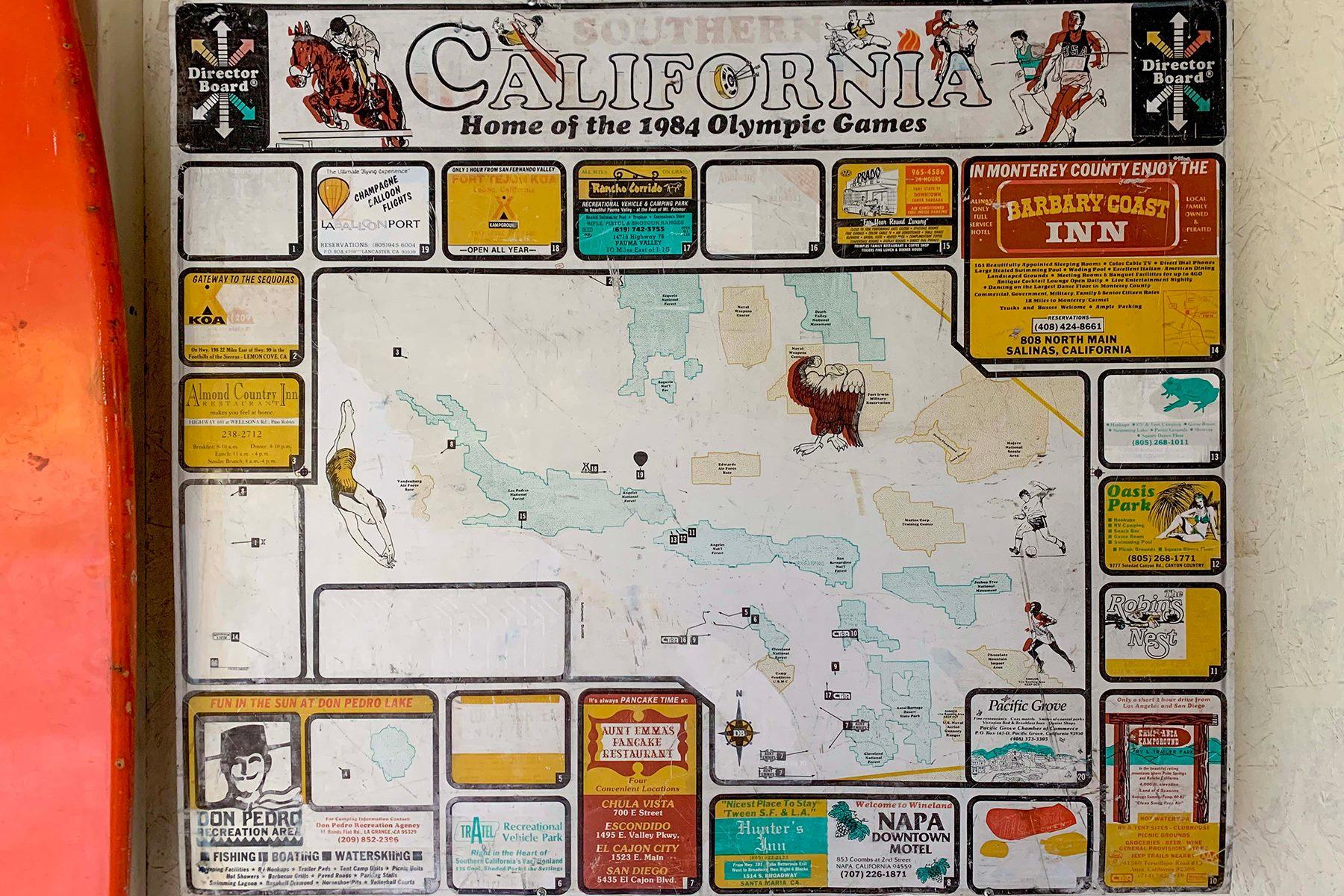
お好み焼き屋兼喫茶店という実に関西っぽい店で

1980年頃、高校生のときに阪神競馬場近くのお好み焼き屋兼喫茶店という実に関西っぽい店で、時給380円でアルバイトしていたが、土曜日の午後の店内は馬券を買った客達の独特の雰囲気に満ちていた。
映画館や行楽地の人混みとも少し違う、満員電車での人の顔とも違う、大なり小なりの運命を他人の手に委ねてただ待つ男たち。その店にはテレビはなく、男たちは持参のラジオをイヤホンで聴きながらコーヒーを飲む。誰かと何かを語り合うでもない。自分の買った馬券が当たった男も、そこで少しの贅沢して酒を飲む、というようなこともほとんどなく、レースが終わってしばらくすると静かに、どこかに去って行く。
そこで出会う大人たちの顔には、家の父や学校の教師たちにはないオーラがあって、カウンターからその顔を見ながらコーヒーを淹れる行為自体が、なにか小説か映画の登場人物に自分がなったような気持ちになった。バイト代は多い月で2万円近くになって、そのほとんどをレコード代につぎ込んでいた。ローリング・ストーンズの「エモーショナル・レスキュー」や、ポリスの「白いレガッタ」、クラッシュの「サンディニスタ」とか。

――神無月につづく。
文・写真:大森克己









