


芋焼酎「佐藤」が愛され続ける理由
-
- 連載 : dancyuムックから
1990年代末、酒の世界に旋風を巻き起こした佐藤酒造の芋焼酎「黒麹仕込佐藤」。若き造り手として活躍してきた佐藤誠さんの芋焼酎への深い愛情と魂を継承し、今、造りを手がけるのは息子・寿峻(としたか)さんの下に結集する若きチームだ。
新しいことをしなければと、焦っていた1年目

「佐藤酒造」ほど元気な蔵を知らない。全社員の平均年齢は35歳。以前からチームで焼酎を造ってきたと豪語するだけあって、結束力が強い。それもそれぞれの個性を引き出して生かす“海賊”のようなチームなのだという。現在、その中心に座るのは、世に芋焼酎「佐藤」を送り出した四代目佐藤誠さんの長男・寿峻(としたか)さんである。小さい頃からずっと「蔵の跡取り」と言われて育った寿峻さんは、高校3年生のときに父親の誠さんから、仕込みの間、毎週日曜日は蔵に手伝いに来るようにと言われた。
「ただひたすら一日中掃除をしていただけなんですが、休憩時間や昼食時に集まった社員さんがみんないい人で、すごく生き生きしていたんです。この人たちとお酒を造る仕事ができるんだったら悪くないなと素直に思いました」
それまで親が敷いたレールの上を進むべきかどうか悩み、進路を決めかねていた寿峻さんが蔵を継ぐことを意識したのは、そのときからだ。大学は父と同じ東京農大醸造科学科に進み、2014年に卒業。東京の料亭で丸2年働く。それは接客の仕事を通して礼儀作法と感受性を身につけてほしいと願う、誠さんの勧めだった。
「仕事はハードでしたが好きでしたね。お店の敷地が広くて、毎日2万歩から多いときは3万歩は料理を運んで歩きました。最初の3ヶ月で体重が15㎏減りました」
会うたびにやせていく寿峻さんを心配して、祖父である先代社長が家に呼び戻す。寿峻さんには、もう少し外で働きたい気持ちもあったが、大学で同じ研究室だった友人がすでに若手杜氏として活躍し始めているのを知り、蔵を継ぐという目標に向かって焦りを感じていた時期でもあったため、家に帰ることに。
「戻ってきたばかりの頃は、会う人ごとに『新銘柄を出さないの』『新しいことをしないの』と言われて、ああ、やっぱりそういうことをしなきゃいけないんだと思っていました。話題性のあるインパクトのあることをしなければ、自分の名前を売らなくては、と焦っていたんです」
1年目は蔵の中で仕込みをしながら、そんなことを考えて悶々としていた寿峻さんは、2年目に入って積極的に外に出たいと思い、社長に直訴する。誠さんは言う。「ある程度仕事を覚えてから、外に出したほうがいいのではないかと悩みました。何ももたないうちに外に出ても、『何も知らないんだな』と言われるだけ。けれど、歳をとってから『知りません』とは言いづらいだろうけど、若ければ『すみません、教えてください』と言える、失敗しても立ち直れる。そのチャンスを親が奪っちゃいけないと思い直しました。息子が蔵に入ったときに教えてくれる人をたくさんつくるために、自分も今まで真っ直ぐに人と向き合ってきたわけですから、その人たちを信じて外に出そうと思ったんです」

飲む人のために焼酎を造るという思い
翌年からは、それまで蔵で働いてきた人たちがずっとつくり上げてきた佐藤酒造の焼酎の立ち位置をまず知ることから始めようと、造りが終わると全国の勉強会やイベントに積極的に参加。さまざまな声に耳を傾ける。さらには特約を結んでいる酒販店、そして飲食店、外部の人たちに会って話を聞いた。それは現・社長の誠さんが長年かけて密に築いてきた信頼関係、その足跡をたどることにもなった。
案の定、まだ経験や知識に乏しかった寿峻さんは痛い目をみる。何もできない不甲斐なさに肩を落として帰ることも多かった。そうしているうちに自らに問うたのは、何のために仕事をしなければいけないのか、自分たちの仕事が何のためにあるのか、ということだった。
「それは社長にもさんざん言われてきたことだったんです。それまで気負って、自分の酒を造ることばかり考えていましたが、そんなことは造りに1、2年入ったくらいでできるもんじゃない。そのために蔵に帰ってきたんじゃないということに気づかせてもらいました。
仕事をするのは飲む人のため。目の前の芋ひとつを切るのも、もろみを混ぜるのも、飲む人のために仕事をする。最終的に飲む人のところで、その酒があったことでどんな時間が生まれるか、会話が生まれるかということで、自分たちは酒を造っているんだと。そこに向かって仕事をしているのが、うちの蔵の強みなんです。そのときに初めて、蔵を継ぐ決心が定まりました」
ちょうど10年前に、本誌(月刊dancyu2009年9月号)の焼酎特集記事で誠さんはこう話している。
――今からは、次の世代に向かって準備を整える時間ですよ。蔵の中でも、外に向かっても。高校生の息子がいつか蔵に入るとき、周囲で彼の先生になってくれる人がたくさんいます。それを考えると、ああ、この蔵の将来が楽しみだなあ、と思えるんです。――
「でもね、よくよく考えれば息子に渡せるものなんてひとつもないんですよ。次の代が自ら獲りに行かないと、得られるものなんてないんです。人との信頼関係は特にそう。一瞬一瞬を積み重ねて、人がどう評価しようが、自分でわかって納得していればいい。それが自然に人となりとなって、信頼関係は出来上がっていくと思う」
誠さんの言葉は静かに心に響く。それは焼酎の新時代を切り拓いてきた重みだろう。「佐藤」が誕生して30年近く。以前に比べれば作業効率も上がり、芋の下処理から蒸留機のバルブの操作まで、細部にわたって造りは少しずつ進化してきた。それでもまだこうして、旨い焼酎を造ろうともがいている。寿峻さんは続ける。
「本当に外の人たちが先生です。うちの蔵は自分たちが旨いと思うものを造って、それを世に出して問うという姿勢です。だから蔵人が若返れば、旨いと思う焼酎も変わってきます。僕は『佐藤』を30年の銘柄で終わらせたくない。さっき社長は『渡せるものなんてひとつもない』と言ったけれど、長年ずっと時間をかけて働きかけてくれたおかげで、やっとスタートラインに立って仕事ができるチームが出来上がった。そのチームで精度を高めてもっと旨い酒を造ろうというところに向かっているから、今、とても楽しい」
そうした思いこそが「『佐藤』はぶれない」という、世の評価を生んでいるのだろう。

「佐藤」といえばお湯割り。おいしく飲んでもらうためにできること。
二人の話を聞き終えて、その晩、天文館の飲み屋で一緒に「佐藤」を飲んだ。誠さんほど上手にお湯割りをつくる人はそういないが、寿峻さんがつくるお湯割りもまたすこぶる旨い。

――改めて聞きますが、「佐藤」はなぜお湯割りをすすめているんでしょうか。
- 誠さん
- やっぱりおいしいからでしょう。本当は鹿児島は前割りのお燗だよね。
- 寿峻さん
- 鹿児島の文化として根づいているから、自然とお湯割りを飲むんですよね。だから「僕らが造る旨い芋焼酎って何だろう」と考えたときに、お湯割りは避けて通れない。お湯割りにしておいしい焼酎を目指して造っている。
- 誠さん
- 温めてやらないと出てこない味があるんだよね。反面、雑味も出るから、お湯割りが一番味がわかる。隠しようがない。蒸留してすぐ飲める蒸留酒は焼酎しかないんだよね。温めて飲む、日常にこんなに溶け込んでいる蒸留酒も少ない。それに温めて飲むって体にもいいんですよ。酔いが回るのが早いから飲みすぎないし。やっぱり、歴史に裏打ちされた文化がなければダメ。だから、その食文化も含めて世界に広めていくくらいの志があっていいと思う。

「佐藤」はビートルズのような立ち位置になりたい
- 誠さん
- 音楽とお酒って似ていると思う。なくても生活できるけれど、なければ暮らしに楽しさや潤いが足りない。たとえばビートルズのように、世代が違ってもみんながいいなと思う音楽、「佐藤」はそういう立ち位置になりたいんだよね。いろんな人がいろんなふうに楽しめる焼酎に。
- 寿峻さん
- 自分たちの世代の多くの人が仕事に対して意味を求めていないと感じる。もちろん、食べるために働くことは必要なことだけど、自分の仕事が何のためにあり、自分の仕事の先には誰がいるか、誰の支えになれているかを考えて、向かうべき方向がはっきりすると、毎日の仕事がとても充実したものになる。やらなければならないんだったら、そういう仕事に携わるほうが人生は楽しい。うちの蔵はそんなふうにやりがいをもって働ける蔵でありたい。また、そこを支えられる酒でありたいと思う。
- 誠さん
- これが正解だと思うことばかりを一直線にやっていたら成功しない。どれを選んでどれを捨てるかが大事。難しい話じゃなくて、本当は愛情や志にしか軸足は置けないでしょう。それをこねくりまわして「こうやったら上手く」というようなことばっかりを追っかけるから空回りする。身のまわりにはそれよりすごく大事なものがあって、それなしには絶対成功し得ないんだよね。遠回りしても、そのぶん勉強しているからちゃんと対応できるんだよ。
――寿峻さんが戻ってから、誠さんは意識して蔵に入らなくなったそうですね。
- 寿峻さん
- それは感じますね。我慢してくれているんだろうな、って。でも、僕は一緒に仕事ができてよかったなと思うんです。子供の頃は家にいなかったし、社長がどういう人間か仕事を一緒にするまで本当にわからなかった。
- 誠さん
- だってね、朝、家を出るとき「また来てね」って、この人は言うんだよ(笑)。オレは漁師になりたいなあ。錦江湾で釣竿握って。
- 寿峻さん
- いつもそう言うんですけれど、みんなで聞かなかったことにしています(笑)。
息子は父の残した足跡を辿り、さらに日々学びながら楽しみながら信頼できるチームと、目標に向かって真っ直ぐに進もうとしている。佐藤酒造の凄味はそこにある。

 お問い合わせ情報
お問い合わせ情報
【住所】鹿児島県霧島市牧園町宿窪田2063
【電話】0995-76-0018
文:瀬川 慧 写真:磯畑弘樹
※この記事の内容はdancyムック「読本 本格焼酎。」に掲載したものです。
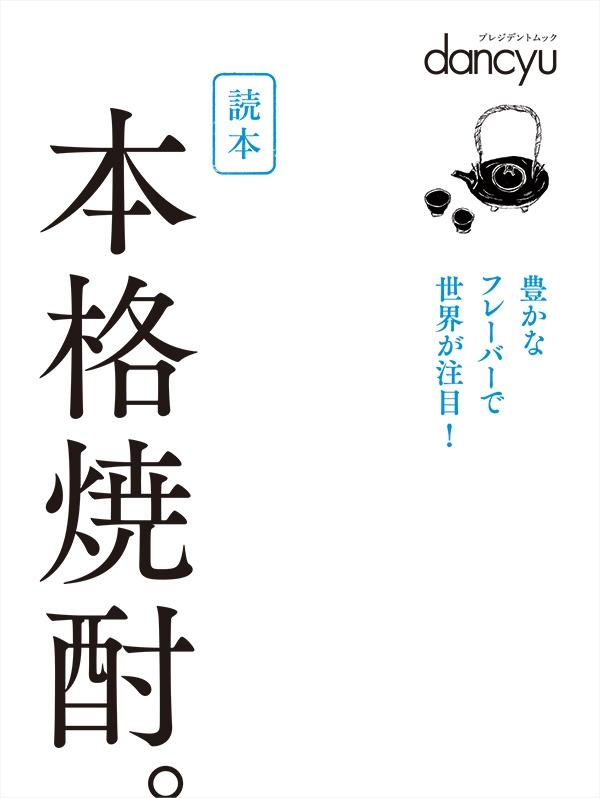
- 読本 本格焼酎。
- B5変型判
2020年04月22日発売/1,430円(税込)









