


【柳田正さん特別登壇】焼酎ファンを震撼させた "2回蒸留"と"樽熟成"。多彩な香りを引き出す超絶マニアックな話。【焼酎の教室・第2回/3限目】
「焼酎の教室」はほぼ月1開催。応募詳細はLINEオープンチャットにて!-
- 連載 : 焼酎の教室
宮崎県の焼酎蔵「柳田酒造」の柳田正さんをゲストに迎え、蔵の背景や焼酎について教わる「焼酎の教室」第2回。3限目は、新しい蒸留方法を追求した“挑戦の2本”篇です。
教える人

柳田正さん(やなぎた・ただし)
1973年、宮崎県都城(みやこのじょう)市で最も古い焼酎蔵「柳田酒造」の四代目次男として生まれる。東京農工大学大学院を卒業後、富士ゼロックスに入社。エンジニアとして4年勤務の後、2001年に家業を継ぐため、帰郷。2010年に五代目代表取締役に就任。
芋焼酎の進化、ここに注目!――①品種の違いが多彩な香りを生む。新品種も開発中!

食いしん坊倶楽部のメンバーに、透明な焼酎と琥珀色を帯びた焼酎が2種配られた。
「続いて皆さんに試飲していただくのは、『mizuiro』と『pentatonic』という焼酎です。どちらも芋焼酎になります」
今、焼酎業界に大きな波がきていると言われるが、特に注目されているのが芋焼酎。2000年代前半に起こった焼酎ブームの頃と比べ、芋焼酎の酒質は大きく変わりつつある。
「その要因は3つある」と、柳田さんは言う。
「一つ目が芋の品種です。焼酎に使われるサツマイモは、果肉が白い白芋、果肉が黄色い紅芋、果肉が橙色をしたオレンジ芋、果肉が紫色の紫芋の4系統あります。とはいえ、約50年もの間、九州の芋焼酎の大半がコガネセンガンという白芋の品種でつくられていました。ところが、ここ10年ほどでコガネセンガン以外のサツマイモで焼酎をつくる蔵元が増えたそうです。その理由は、芋の品種によって生じる焼酎の香りが異なることがわかってきたからです」
紅芋はリンゴやはちみつのような甘酸っぱい香り、オレンジ芋は南国のフルーツ、紫芋はヨーグルトのような香りといったように、芋の系統や品種によってバラエティー豊かな香りが楽しめるようになり、新たな飲み手が増えたことにある。研究機関によって芋焼酎の香りの分析が進んだことも影響している。
「焼酎用のサツマイモの品種は現在も開発されています。焼酎ファンがあっと驚くような新たな芋が近々誕生するかもしれませんよ」
柳田さんは目を輝かせながら、最新トピックスをメンバーに教えてくれた。
芋焼酎の進化、ここに注目!――②魅惑の香りを育む芋の熟成

「二つ目が芋の熟成です。明治時代から令和の時代まで、焼酎に使うサツマイモは新鮮であればいい焼酎になると信じられてきました。ですが、収穫してから一定期間おいて熟成させたサツマイモで焼酎を仕込むと、新鮮な芋では出せないライチのような香りや濃厚な蜜のような甘い香りを出せることがわかりました」
熟成というアプローチで、これまでにない新しい香りを表現できるかもしれない、と期待を寄せる。
芋焼酎の進化、ここに注目!――③新しい蒸留方法で、欲しい香りを抜き出す
そして、三つ目が、今回の本題である蒸留というテクニック。
「皆さんに飲んでいただいている焼酎は、蒸留で芋焼酎の可能性を見つけるための、挑戦の2本です」


通常、芋焼酎の蒸留には4時間ほどかかる。蒸留を始めて序盤に垂れてくる液体を「初垂れ(はなたれ)」といい、焼酎の大部分を占める中盤の液体を「本垂れ」、終盤を「末垂れ」と呼ぶ。
「焼酎の蒸留においては、初垂れ、本垂れ、末垂れで留出される香気成分が異なります。初垂れはエステル類を多く含みます。日本酒を飲む人ならご存じだと思いますが、メロンやバナナやリンゴのような香りですね。本垂れに移っていくと芋焼酎らしい甘い香りが増えていき、末垂れでは香ばしい香りに変わっていきます」
一方、アルコールは、初垂れの留出が一番多く、徐々に減っていく。アルコール度数は初垂れで60%後半、最後は0%になるのだが、アルコール度数が8~10%で蒸留を終える蔵元がほとんどだ。
「昔の職人は、末垂れの香りを『馬糞臭』と呼んでいました。末垂れの香ばしい香りが増えてくると、名前の通り、好ましくない香りが感じられ、焼酎の風味を損ねてしまいます。アルコール度数が約10%まで下がってくるとその香りが強くなってくるので、蒸留を終わらせなさい、と教わりました」
柳田さんの挑戦の第一歩、「mizuiro」は、『千本桜熟成ハマコマチ』から生まれた

4時間という蒸留の過程で、刻一刻と留出される香りが変化していくことは経験からも知っていた。そこで柳田さんが思いついたのが、「蒸留の過程で、欲しい香りが留出する特定の区分を抜き出し、焼酎にする」というもの。これが「mizuiro」という銘柄だ。
「透明のほうが『mizuiro』です。ぜひ、味わってみてください。ラムネのようなニュアンスを感じませんか」
焼酎が注がれた容器を鼻先に近づけ、すーっと嗅いでみる。甘い香りを拾ったところで、今度は一口含ませ、舌の上に液体を広げると、サイダーのような爽やかさが鼻孔に抜けていく。
柳田さんの言葉にメンバーたちが深く頷くと、
「柳田酒造には『千本桜熟成ハマコマチ』という芋焼酎があります。これは、ハマコマチというオレンジ芋を一定期間熟成させてから仕込む焼酎ですが、『mizuiro』も同じ芋で仕込んでいます。大きな違いは、蒸留です。初垂れ、本垂れ、末垂れまで蒸留した原酒でつくるのが『千本桜』であるのに対し、『mizuiro』は特定の区分の原酒を抜き出してつくります」
花や果実、ヨーグルトにバター、はちみつまで。焼酎が持つ多彩な香り成分

焼酎は香りの酒、と柳田さんは言う。
「スライドをご覧ください。これは酒類総合研究所が作成した本格焼酎・泡盛のフレーバーホイールで、焼酎の香りを言語化して円形に配列したものです」
フレーバーホイールには、花や果実、乳製品など、さまざまな香りが記されていた。焼酎の香りが実にバラエティー豊かであるかがうかがえる。
芋焼酎の香りを捉えるうえで、焼酎蔵が注目している香気成分が三つある、と柳田さん。
- リナロール
柑橘、ラベンダー、スズランなどにたとえられる。中世ヨーロッパの貴族は花から抽出したリナロールにリラックスや安眠効果を見出した。焼酎用に開発された「ジョイホワイト」というサツマイモでつくった芋焼酎に特に多く含有する。
β-ダマセノン
甘みを感じる香気成分。はちみつやわたあめ、りんごのコンポートなどにたとえられる。
β-イオノン
オレンジ芋由来の香気成分で、スミレにたとえられる。
※オレンジ芋の仲間であるタマアカネやハマコマチの焼酎は、紅茶や南国フルーツのような香りが特徴としてあげられる。これらの香りは三つの香気成分が組み合わさることで生成されると考えられる。
話を「mizuiro」に戻そう。
「満を持してつくってはみたものの、思ったほど香りがのっていないと感じました」と、柳田さん。
「せっかく狙った香りを抜き出したのに、仕上がった焼酎は香りも弱く、もの足りないものでした。通常の『千本桜熟成ハマコマチ』のほうがよっぽど香り高い。その理由がわからなかったんです」
「pentatonic」は、そんな「mizuiro」の反省点が生かされた焼酎と言う。
従来とは一線を画する、香り鮮やかでリッチな焼酎「pentatonic」誕生秘話
「pentatonic」は松露酒造(宮崎県串間市)の矢野裕晃さんと宮崎県食品開発センターが共同開発し、2023年に初リリースされた商品。通常、伝統的な焼酎は1回蒸留であるのに対し、蒸留を2回行う画期的な1本である。
開発のきっかけとなったのが、泡盛蔵の有志がつくった「尚」という泡盛だ。泡盛を複数回蒸留することで特有の硫黄臭やオイリーさを抑制し、クリーンで甘い香りを際立たせることに成功した。これを指導したのが、当時沖縄国税事務所の鑑定官だった宮本宗周先生(現・熊本国税局主任鑑定官)。この手法を芋焼酎に取り入れたらどうだろうか。そう考えた柳田さんは矢野さんとともに宮本先生に教えを請い、2年ほどかけて「pentatonic」の第1弾を完成、リリースさせた。
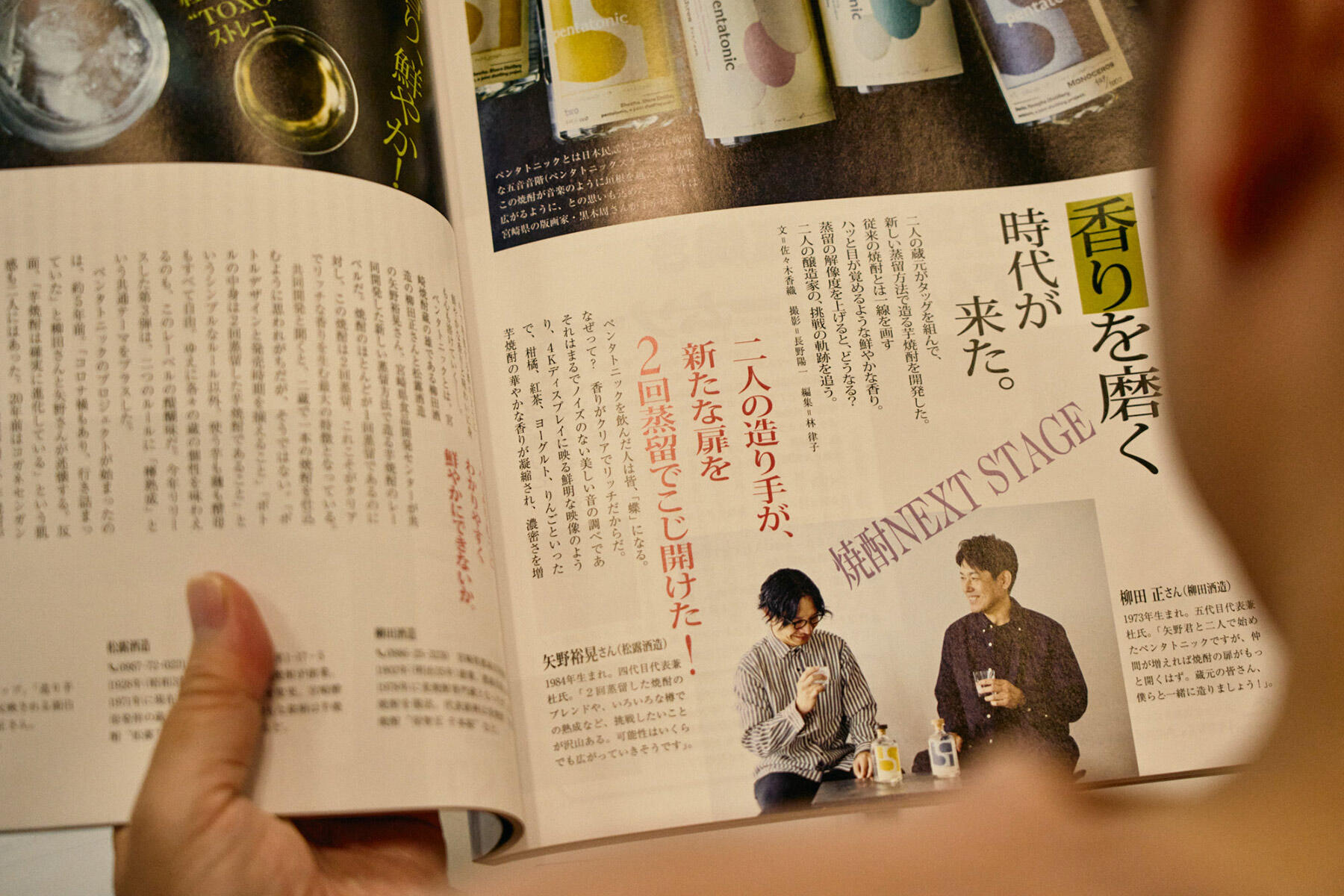
柳田さんは「pentatonic」をつくるうえで、学んだことがあった。
「焼酎の香気成分をつくるには、蒸留による熱が必須だということ。もろみに十分に熱を与えないと、香りそのものが生成されないんです。特に、先ほどご説明したリナロールという香気成分は熱なしでは生成されない香りです。『mizuiro』のように蒸留の途中で、ピンポイントで抜き出してしまっては、その後にも生成されるリナロールをみすみす逃してしまっていることになるわけです」
まずは1回目の蒸留で焼酎の香気成分をつくり、でき上がった焼酎の原酒を再び蒸留機に入れ、2回目の蒸留にかけて狙った香りを抜き出す。こうすることで従来の焼酎とは一線を画する、香り鮮やかでフレーバーリッチな焼酎が爆誕したというわけだ。

「琥珀色をしたほうが、『pentatonic』の第3弾であるTOXOTISです。この焼酎は『mizuiro』と同じくハマコマチというオレンジ芋を使用しています。2回蒸留でリナロール、β-イオノン、β-ダマセノンの香りを狙って抜き出し、その原酒をさらにバーボン樽に貯蔵させました」
試飲をしていたメンバーから、こんな質問が投げかけられた。
「2回蒸留して狙った香りを得られたのに、さらに樽に貯蔵したのはなぜですか」
鋭いご質問ですね、と柳田さん。
「実は2回蒸留すると、酒の飲み口が軽くなるんです。その理由は、前にお話しした末垂れで得られる香ばしい香りをカットするから。あの香りは、焼酎という酒に厚みや余韻をもたらします。一方で『pentatonic』は狙った香りのみを味わってもらう焼酎ですから、末垂れの香りはいらない。では、どうやって2回蒸留した焼酎にボディ感を付加させるか。矢野さんと一緒に考えました」
考えついた方法が、次の三つ。
「一つ目が熟成。タンクの中で原酒を熟成させると、確実に焼酎に厚みが出てきます。ただし、最低でも3~5年の年月がかかりますので、完成までずいぶん待たなければなりません。
二つ目がブレンドです。さまざまな原酒をブレンドすることで焼酎に厚みを出す作戦です。これは近々試してみようと思っていますが、やはり試作に時間がかかります。
そして、三つ目。これが今回おこなった樽貯蔵です。樽に原酒を寝かせることで樽由来のコクと甘い香りが加わり、焼酎がふくよかな味わいになります。ウイスキーのように長く寝かせなくても、短期間でその効果を得ることができるんです」
芋焼酎は透明な酒であるべきで、樽に寝かせようものなら芋の朗らかな甘みが木樽のえぐみに負けてしまうのではと柳田さんは考えていたが、バーボン樽は違っていた。
試飲するとよくわかる。トップにくるのは樽特有の木の香りだが、口腔内から鼻に抜けるのは、華やかなオレンジ芋由来の香りだ。柳田さんが「芋焼酎が大化けした」と語るように、香りの幅も奥行きも深みもすべて増していることに気がつく。

樽の話のあとで、メンバーからこんな質問が寄せられた。
「複数回蒸留をしたり、樽で寝かせたりするのは、海外の洋酒を意識されているからでしょうか。焼酎も世界の舞台に上がれるように、いろいろと試されているのですか」
「いいご質問ですね」。柳田さんが笑顔を見せる。
「ウイスキーやラムなど世界中で愛されている蒸留酒と同じ舞台に焼酎を引き上げたくて、私たち蔵元は10年ほど前から海外シェアを獲得するべくさまざまな取り組みをしてきました。アプローチの仕方は色々ありますが、まずは海外の人が慣れ親しんでいる味と香りと色で焼酎のハードルを下げたいというのが理由です。
また、焼酎は料理と合わせることのできる、世界的に珍しい蒸留酒です。サツマイモの品種違いや蒸留方法によって多彩な香りを生み出せる芋焼酎は、ワインと同じように食事とのペアリングも楽しんでいただけるはずです。
こうして世界中の方に焼酎を知っていただき、最終的には日本の伝統的な焼酎にまでたどり着いてほしい。樽熟成にはそんな思いも込められています」
海の向こうで愛される焼酎――。そんな未来像を描きながら、日々、造りにまい進する柳田さんが、蔵の未来に思いを馳せながらつくる「偏愛の2本」を、次回ご紹介します。
文:佐々木香織 撮影:竹之内祐幸 構成:林律子









