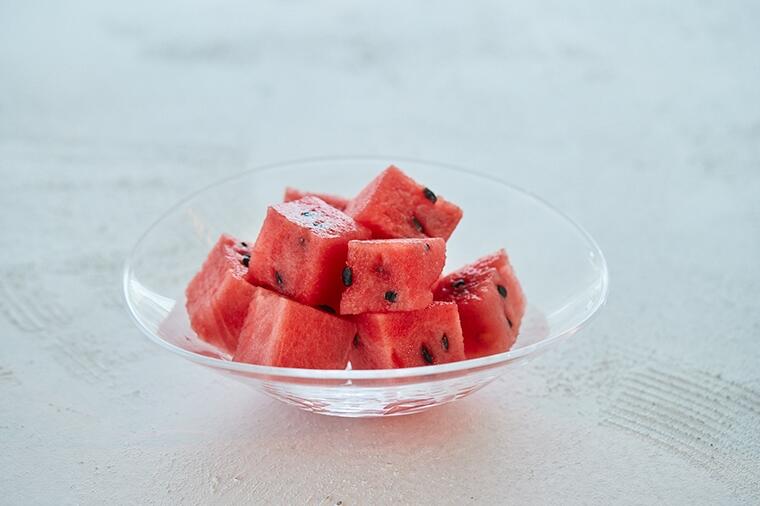もっちりした和風スクランブルエッグ"なたね"|ライター・上島寿子
-
- 連載 : 一生食べ続けたいひと皿
ライターの上島寿子さんのひと皿は、お母様から受け継いだ「なたね」。特別なときに食べるハレの料理でもなく、いつもの普段の食事でもなく、ただ美味しいとか、好きだとか、ということでもなく、常に身近にあって食べ続けたいもの。人生や思い出と、いつも、いつでも結びついている。そんな、一生食べ続けたい「ひと皿」を食いしん坊に聞きました。
つくり、食べ続けたい母のひと皿
母は東京・銀座育ちではあるけれど、つくる料理には関西の味が多い。大阪の北新地で生まれた父の味覚に合わせたのだろう。ただ、もともと食への探究心が強い人だから、繊細な関西の味に惹かれたのかもしれない。
象徴的なのはお正月のお雑煮だ。元旦は東京らしく小松菜入りのおすましが出てくるのだが、翌日は関西風の白味噌仕立てに替わる。具材は大根、人参、里芋も入っていた。お餅は本来、丸餅だが、昔の東京では手に入りにくく、そこははしょって角餅に。ともあれ、こっくり甘い白味噌のお雑煮も“わが家の味”だったのである。
ちなみに、三日目は鶏ガラでだしを取ったお雑煮をつくるのが決まり。これは単に「毎日同じ味だと飽きるから」だそうで、子供の頃は三が日とも違うお雑煮を食べるのが当たり前だと思っていた。
そんな母から受け継いだ料理の一つに“なたね”がある。つくり方は至ってシンプル。卵1個に対して醤油をひと回し。油はひかず、こびりつきにくいフッ素樹脂加工の鍋でとろりと半熟状に火を入れる。平たくいえば和風のスクランブルエッグだ。それだけで食べてもおいしいけれど、炊き立てのご飯にのせればもう最高。ねっちりとしたなたねがご飯に絡み、お米の甘味を引き立たせてくれる。
考えてみれば、味としては卵かけご飯と一緒だからご飯を呼ぶのは当然。でも、冷たい卵かけよりほんのり温かいなたねのほうが断然好きで、朝食になたねが並ぶとご飯をいつもより多めによそっていた。
それが関西の味だと知ったのは、大人になってからだ。母によれば、結婚して間もない頃、父の家で「息子(父のこと)の好物」と教えてもらったという。だから、これが大阪で一般的なのかオリジナルなのかはわからない、と。調べてみると具材の入った炒り卵のことをなたねと呼ぶようで、うちのはその派生形なのだろう。
私も結婚してから、このなたねを自分でつくるようになった。鍋で火を入れて半熟状になったら取り出すだけだから簡単と思っていたら、これが意外に難しい。緩いともっちり感が出ないし、火を入れすぎたらぽろぽろに。どんな料理もそうだけれど、加減が大事というわけだ。
あるとき、母に改めてなたねのつくり方を見せてもらったことがある。すると取り出したのはなたね専用の箸。割り箸を切って先を尖らせ、4本を輪ゴムでとめた自作の道具だ。母曰く、先の尖り具合、長さ、箸の開き具合、すべてがなたね仕様になっているという。こんな秘密兵器があったとは。

火の入れ方にも違いがあった。とろ火でゆっくりゆっくりと加熱して途中で火から外しながら、なたね箸でひたすらくるくる、くるくる。私といえば朝の忙しさからついつい火を強くして、かき混ぜ方も大雑把。それが仕上がりの違いに表れていたのか。
母は83歳になった今も毎朝、台所に立ち、父と自分、2人分のなたねをこしらえている。食べる人を思って、簡単な料理でも、いや簡単だからこそ丁寧に料理する。その大切さを見つめ直せるから、私もなたねをつくり続けていく。おそらく永遠に母の味は越えられないと思うけれど。

文・写真:上島寿子