

最高の環境と職人技が生み出すイベリコハムの感動
- Sponsored by イベリコ豚インタープロフェッショナル協会
イベリア半島原産の世界でも希少な種である、イベリコ豚からつくられる“イベリコハム”。伝統と自然環境に育まれたその魅力とは。
情熱と愛が込められた美味なる逸品
地中海の美食の象徴であり、ヨーロッパ料理の伝統の象徴でもあるイベリコ豚の生ハムは、卓越した風味とまろやかな食感で知られる。加えて、さまざまな料理の味を引き立ててくれることから、重要な食材として世界で高く評価されているのだ。
原料となるイベリコ豚は、主にイベリア半島に生息している特有の在来種で、南西部に広がる“デエサ”と呼ばれる、約350万haのオークやコルクの木がある牧草地で放牧されて育つ。最古の持続可能な生態系である“デエサ”はイベリコ豚が育つための最高の天然資源が揃っており、飼料として使われるものは厳重に管理されている。イベリコ豚もこの環境の多様性を支える存在であり、大自然の中を1日10kmも走り回り、どんぐりの実を8~9kgも食べるイベリコ豚自身にとっても楽園である。

イベリコ豚の生ハムは、鮮やかな赤い色と、他のハムにはない“白い繊維状の脂肪”が特徴。この赤身と脂肪のバランスがもろく柔らかい食感を生み、口の中を覆う刺激的な風味を醸し出すのだ。こうした唯一無二の味わいは、豊かな自然環境と、保存のための塩以外の添加物を一切使用せず、3年から5年もの歳月をかけた職人技によってつくられる。

「イベリコハムは、独自の生態系であるデエサ、畑、農場と密接に結びつき、ヨーロッパの持続可能な生産基準を尊重した、伝統製法で生産されています。シンプルな料理から高級レシピまで、どんな料理も格上げしてくれる底力があり、その多様性と品質の高さは、紛れもなく美食のシンボル。洗練された味わいと美しい盛りつけ、食材の信頼性が重視される日本のレストランや家庭で、きっと愛されることと思います」
そう話すのは、イベリコ豚インタープロフェッショナル協会(ASICI)のラウル・ガルシア会長だ。

最もポピュラーなイベリコハムの食べ方のひとつは、薄く均一にスライスし、口の中で溶けるくらいの常温でシンプルに提供すること。そうすることで生ハムの複雑な香りや絹のような食感、深みのある味わいが引き出されるという。また、トーストしたパンにフレッシュトマト、イベリコハムをのせ、エクストラバージンオリーブオイルをかけた“生ハム入りパンコントマテ”もクセになるおいしさ。
「イベリコハムは日本人の味覚に合わせた創作料理の分野でも無限の可能性を秘めています。たとえば、鮨や刺身のタネとして使えば、その繊細なスライスが風味と食感にコントラストを。ラーメンやうどんに加えれば、スープに深い旨味をもたらします。生ハムの自然な甘味が引き立つサラダやデザートもお薦めです」
イベリコハムが完成するまでの長い期間には、その土地や生活、農家の情熱や愛が込められている。イベリコハムが文化であり、伝統であり、職人技だと言われるゆえんはここにある。
イベリコ豚の故郷を訪ねたアンバサダー、吉田能さん

2024年12月、日本市場におけるイベリコハムのアンバサダーに選ばれた3名が、そのルーツを知るべく、現地を訪れた。アンバサダーに選ばれたのは、東京・白金台のレストラン「CIRPAS」の吉田能シェフ、アーティストの野原邦彦氏、フードアーティストの諏訪綾子氏。彼らはマドリッドから車で2時間ほど離れた大学都市・サラマンカを基点に、イベリコハムの背景、文化、自然などのルーツをたどった。今後はおのおのの活動を通して、この経験とイベリコハムの魅力を日本市場に伝えていくという。今回、料理のプロとしての視点から吉田能シェフに旅の感想、そしてイベリコハムの可能性を聞いた。
「今回のスペイン訪問は僕にとって3回目です。最初は、中学生くらいのとき。父親の仕事について2週間ほど、もちろん遊びに来ただけですけどね。その後、自分の仕事でフランスにいたので、ヨーロッパの文化というか背景についてはある程度理解しているつもりだったのですが、今回改めてスペインを訪問して、ああ、フランスと違う、と。スペインという国の文化をしっかり感じました。料理もシンプルだけれど、食材の旨味がしっかりあっておいしいと思いましたね」
吉田シェフは伝統的なフレンチを得意とする店でシェフを歴任。パリ滞在経験もある彼にとっても、スペインの肥沃な大地は印象的だったようだ。
「デエサではイベリコ豚をずっと見ていました。デエサって、アグロフォレストリーですよね。無理な開拓をせず、自然な地形を生かして酪農や林業、農業などを循環させる。マダガスカルのバニラ栽培もそうだし、日本でも小規模ですがやっているところがあります。このイベリコ豚のデエサはそのルーツともいえるべき伝統的なもの。最近のアグロフォレストリーはデエサが見直された動きでしょう。イベリコハムについては昔から旨味が強くておいしい印象は持っていましたが、実際にイベリコ豚を育てている人に会って、豚が育ったどんぐりの木の下に立って、豊かな土壌に触れてみて、これからはこの背景や自然、歴史などの付加価値をのせて、日本の皆さんに魅力を伝えなければ、と思います」
イベリコハムの育つ環境に大きな感銘を受けたという吉田さん。最後に訪れたイベリコハム工場での感想、そして日本でのイベリコハムの楽しみ方を聞いた。

「今回現地を訪れて、餌や飼育法、血統によって4つに色分けされた品質管理タグがあることを初めて知りました。工場につるされたハムについているのが黒いタグなら『放牧されてどんぐりや草のみを食べて育った』『血統100%のイベリコ豚』、赤なら『放牧されてどんぐりや草のみを食べて育った』『血統75%あるいは50%のイベリコ豚』とか。これによって脂ののりや旨味の強さなども変わる。こんなことも日本の皆さんにも知ってほしいですね。驚くほど旨味を持っている食品なので、食べ方は現地と同じようにあまり手を加えず食べるほうがいいと思っています。自分の料理に加えるとしても、完成された状態の料理に添える、というのがベストかな。イベリコハムは決して安価なものではないので、家庭で日常的にってわけにはいかないと思うんですよ。いつもと違う話がしたいときなんかに、特別な雰囲気をつくってくれるアイテムだと思います。あ、あと今回、すごくいい発見だったのは、イベリコ豚の骨を煮てブイヨンを取ったスープ!塩をいれなくてもしっかり味がして、すごくおいしかった。捨てちゃうような部分を煮込んでクリアなブイヨンにする、いいですよね。前日にこのブイヨンに甘海老を足したスープも頂いたのですが、これは今回一番面白いと思いました。今後また日本の皆さんに、自分が感じた魅力を伝える場がつくれればいいなと思っています」
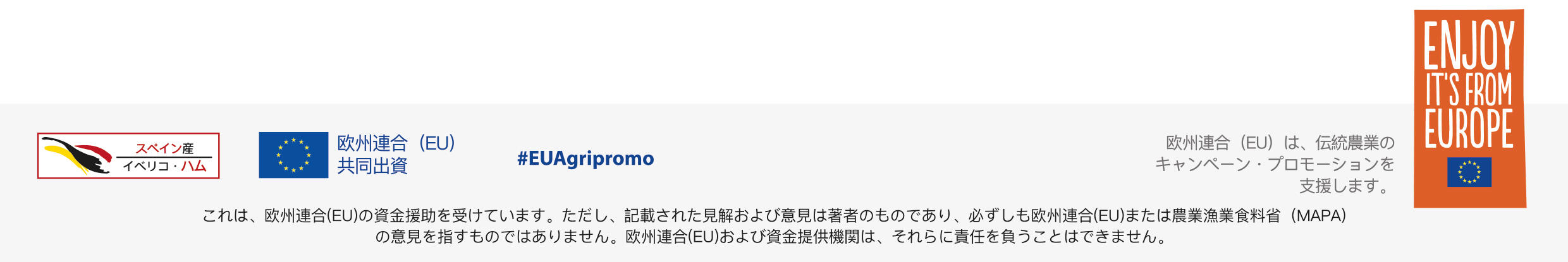
文:REVE、編集部






